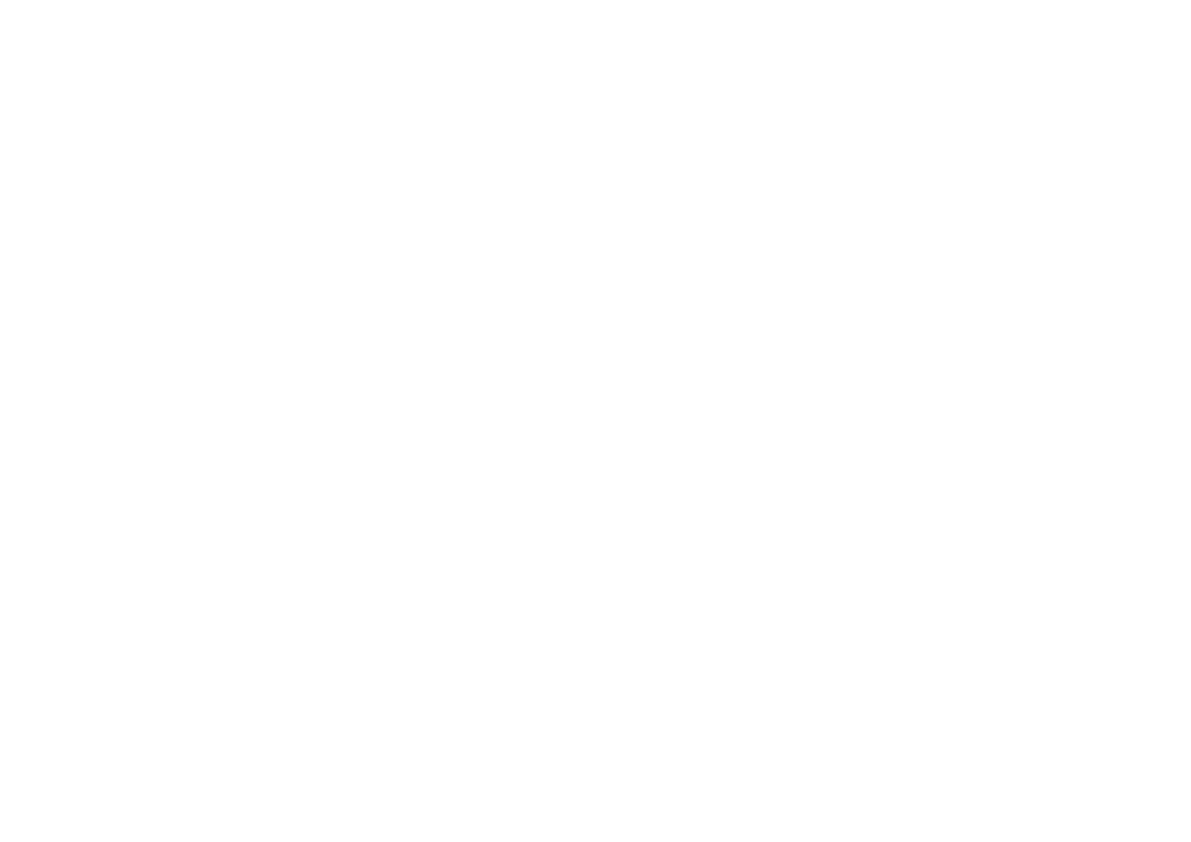会社を経営していると、以下のような疑問を持つこともあるでしょう。
自社の業績改善を図りたいけど、経営分析ってどうやるの?
経営分析って何で必要なの?
結論、経営分析は自社の経営状況に関する数字を用いて客観的に把握し、今後の経営方針を決めるために必要不可欠です。経営分析の方法は主に5つあり、目的に応じて使い分けなくてはなりません。
しかし、具体的にどうやって分析すればいいかわからない方も一定数いるでしょう。
本記事では、経営分析を行う目的や方法、効率的に分析するためのツールを紹介します。業績を上げたいけど、何から始めていいかわからない方は、ぜひ参考にしてください。
経営分析とは【財務分析との違い】

財務分析と経営分析は、企業の経営状態を評価するための手法ゆえ、度々混同されがちですが、対象範囲に違いがあります。
財務分析は、財務諸表から得られる数値を分析し、企業の財務状況を評価することに重点を置いています。一方、経営分析は企業や組織の経営状態を定量的なデータを用いて分析・評価し、その改善策を立案することです。
そのため、財務分析は企業の財務状況を評価することに特化した手法であり、経営分析はより総合的な視点で企業の経営状態を評価しています。
位置づけとして、経営分析の中に、財務分析が内包されていると考えて良いでしょう。
経営分析を行う目的

経営分析の意味を理解しても、目的が分からないまま分析をすると効果が半減してしまいます。
そこでここからは、経営分析を行う主な目的を3つ解説します。
自社の強みと弱みを明確にするため
経営状態を把握し戦略の見直しを図るため
縮小するべきか拡大するべきか判断できる
経営分析を行う目的を正確に認識すれば、分析する際に着目すべきポイントを理解でき、効率良く作業を進められます。
自社の強みと弱みを明確にするため
自社の強みと弱みの明確化には以下のようなメリットがあり、企業経営において大変重要です。
強みを活かした事業展開ができる
競合優位性の向上が期待できる
自社の成長性や収益性を向上させるための解決を見つけられる
たとえば、自社の強みが技術力である場合、その技術力を生かして新商品の開発やサービスの改善を行うことで、競合他社との差別化を図れるでしょう。
また、弱みが人材不足である場合、採用や教育制度の改善に取り組むことで、人材確保や社員のスキル向上、離職率の低下が期待できます。
自社の強みと弱みを明確にすることは、企業経営において重要要素の一つであり、それを踏まえた経営戦略の立案が必要です。
経営状態を把握し戦略の見直しを図るため
経営状態を把握することで、戦略の見直しを図ることができ、業績の向上に繋げることが可能です。
たとえば、経営分析によって収益性が低いことが判明した場合、経費の削減やマーケティング戦略の改善などに取り組むことで、収益性の向上が図れます。
また、キャッシュフローの改善が必要な場合、資金調達や債権回収などの対策を講じることで、資金収支の管理がしやすくなり、改善が見込めるでしょう。
このように経営状態を経営分析によって正確に把握し、戦略の見直しを図ることで、業績の向上や企業価値の向上を目指すことも可能です。
縮小するべきか拡大するべきか判断できる
経営分析を行うことで、企業が事業を縮小または拡大すべきか判断できます。 縮小すべき場合は事業の再構築を、拡大すべき場合は投資の拡大を検討しなければなりません。
例として、財務分析により収益性の低下が判明した場合、事業の縮小を検討する必要があります。 一方、自社が成長している市場で、市場シェアの拡大が見込まれる場合は、投資を拡大してシェア率の増加を目指せるでしょう。
経営分析の5つの手法と見るべき指標

前章で、経営分析の目的について解説しましたが、経営分析の目的と手法はセットで考える必要があります。目的だけが明確で手法が不明瞭だと、その目的を十分達成することは難しいと言えるでしょう。
ここからは経営分析の具体的な手法と確認するべき指標をそれぞれ5つ紹介します。
収益性分析
安全性分析
成長性分析
生産性分析
活動性分析
5つの分析手法を適切に使い分けて、会社の正確な経営状況を理解しましょう。
収益性分析
収益性分析とは、企業の収益性を評価する分析手法です。会社がどの程度稼ぐ力を持っているか示す指標のことを指し、以下のような式で導き出せます。
指標名 | 式 | 簡易な概要 |
売上高総利益率 | 売上総利益÷売上高×100 | 粗利益が売上高に占める割合を示す指標 |
売上高営業利益率 | 営業利益÷売上高×100 | 売上高に対する営業利益の割合を示す指標 |
収益性が高いと効率的に利益を生み出せている状態であり、収益性が低い場合はコストが割に合っていないと考えられます。
安全性分析
安全性分析とは、企業の負債と資本の構成や比率を収集・分析することで、返済能力や財務面の安定性を評価できる分析手法です。すなわち、企業の支払い能力の安定性を示す指標となります。
指標名 | 式 | 簡易な概要 |
流動比率 | 流動資産÷流動負債×100 | 短期的な会社の支払い能力を示す指標 |
自己資本比率 | 自己資本÷総資本×100 | 総資本に対して、返済不要の自己資本の割合を示す指標 |
成長性分析
成長性分析とは、企業の成長性を評価する分析手法で、現在から将来への成長率を示す指標です。
具体的には、下表のような指標を分析します。
指標名 | 式 | 簡易な概要 |
売上高増加率 | (当期売上高-前期売上高)÷前期売上高×100 | 前期に対しての売上高の伸びを示す指標 |
経常利益増加率 | (当期経常利益-前期経常利益)÷前期経常利益×100 | 前期の経常利益と比較しての増減割合を示す指標 |
自社の指標の高低だけでなく、市場の成熟度合や競合他社を考慮した検討が必要と言えるでしょう。
生産性分析
生産性分析とは、企業の生産活動における生産性を評価するための分析手法で、会社の基本資源の人・物・金をどれだけ有効活用できているか示す指標であり、下表を分析します。
指標名 | 式 | 簡易な概要 |
労働生産性 | 付加価値÷従業員数×100 | 従業員1人あたりが生み出す成果を示す指標 |
資本生産性 | 付加価値額÷総資本×100 | 投入した資本金に対してどれだけ付加価値が生じているかを示す指標 |
自社の基本資源を余すことなく使えているか確認できるので、企業の現状を把握する上で、重要な指標と言えるでしょう。
活動性分析
活動性分析とは、企業が業務を執行する上で必要な流動資産の運用状況を評価するための分析手法で、資本が有効に運用されているか示す指標です。
指標名 | 式 | 簡易な概要 |
総資本回転率 | 売上高÷総資本×100 | 資本が期中に売り上げとして何回回収され再投資されるかを示す指標 |
固定資産回転率 | 売上高÷固定資産×100 | 売り上げを用いて固定資産を無駄なく活用できているか示す指標 |
資本が円滑に回っていることは、企業運営において優先度合が高いです。資本が上手く回らないと、キャッシュアウトから倒産してしまう可能性も考えられます。
経営分析を効率よく行う方法

ここからは経営分析の手法を、効率よく行う方法を4つ紹介します。
正確な数値の財務諸表を用いる
自社にあった指標を利用する
分析ツールを活用する
フレームワークを利用する
分析をする際のポイントを押さえて、経営分析をより正確かつ効率的に進めましょう。それでは一つひとつ見ていきます。
正確な数値の財務諸表を用いる
正確な数値の財務諸表を用いることで、経営分析を効率的かつ正確に進行できます。
分析の最も根幹になるのは「数字」なので、少なくとも財務諸表の数字は正確でなくてはいけません。この数字がずれていると、分析結果が本来の数値と異なってしまい、次の施策へ影響を及ぼす可能性があります。
最悪の場合、誤った施策を打ってしまい、希望するほどの利益を得られないことや赤字を被る可能性があるため、常に正確な数値を財務諸表に記録して保管しておきましょう。過去に作成した財務諸表が必要なこともあるので、古いものも確実に管理してください。
自社にあった指標を利用する
前章で紹介した指標を全て使うことが、必ずしも良いわけではありません。企業によって業種や会社規模、抱えている課題が異なるので、自社に適した指標を選びましょう。
加えて、自社にあった指標を利用することで、次の2つの理由から経営分析を効率的に行えます。
分析結果がより正確になる
経営戦略の策定がしやすくなる
たとえば、自社が製造業である場合、生産性や原材料の消費量など生産関連に対する指標を算出し、それに基づく改善目標を提示すると良いでしょう。
また、経営戦略の施策を改善したいのであれば、各数値を同業他社と比較し、著しく低い項目を抽出すると効果的な施策の策定につながります。無駄な時間と手間を減らせるので、自社にあった指標を利用しましょう。
分析ツールを活用する
経営分析は、分析ツールを活用すれば効率的かつ正確に行えます。
エクセルを使って手作業で分析を行うと、多くの時間や手間がかかるだけでなく、ミスも発生しやすくなるでしょう。一方、専用の分析ツールを活用すれば、財務諸表と連携させることによって、自動的にデータを収集・作成できるので、ミスなく分析できます。
新しいシステムを導入することに抵抗がある方もいるかもしれませんが、分析ツールがもたらすメリットを考えると、導入する方が妥当です。
分析ツールと言っても、それぞれ特色や使い方が大きく異なるため、各製品について詳しく調べてから導入しましょう。企業のHPや口コミなどを参考に選ぶと失敗する確率を下げられます。
フレームワークを利用する
経営分析に適したフレームワークを利用することで、ある程度の経営判断を自己分析するできます。
フレームワークに沿えば、一定の質が担保されるうえに、無駄な手順を踏んでしまう心配もないので、生産効率も向上するでしょう。
具体的には、SWOT分析やBCGマトリックスなどのフレームワークを用いることで、企業内外の要因を整理し、戦略の策定に役立てられます。自身の目的に合うフレームワークを選択して、それに沿って分析することで間違える可能性が低く、かつ一定品質の分析が可能です。
経営分析ツールなら「SubFi for Business」がおすすめ

本記事では、経営分析を行う目的や効率よく行う方法を解説しました。
結論、経営分析は滞りなく企業を運営するためには必要不可欠です。自社の課題解決に必要な分析方法を使い分けて、効率よく分析を行いましょう。しかし、経営分析は正確な数字が必要で手間がかかるので、人力でやることはおすすめしません。
そこで、経営分析を効率よく行いたい方には「SubFi for Business」がおすすめです。
「SubFi for Business」は、使用しているSaaS/サブスクをマイページから一元管理できる経営分析ツールです。
本来、企業の経理企画部や経営者自身が担っていた下記3つの仕事を「SubFi for Business」が自動で行います。
支出データの収集
データの蓄積
データの整形
また、高水準な経営判断の材料を提供するために、下記の2つの機能も搭載されています。
同業他社の支出平均を調べられる機能
同業他社に人気のITツールを確認できる機能
SubFi for Business」は、経営企画部や経営者が他の施策検討に時間を使え、経営判断材料として精度が高く適正な情報を提供が可能です。