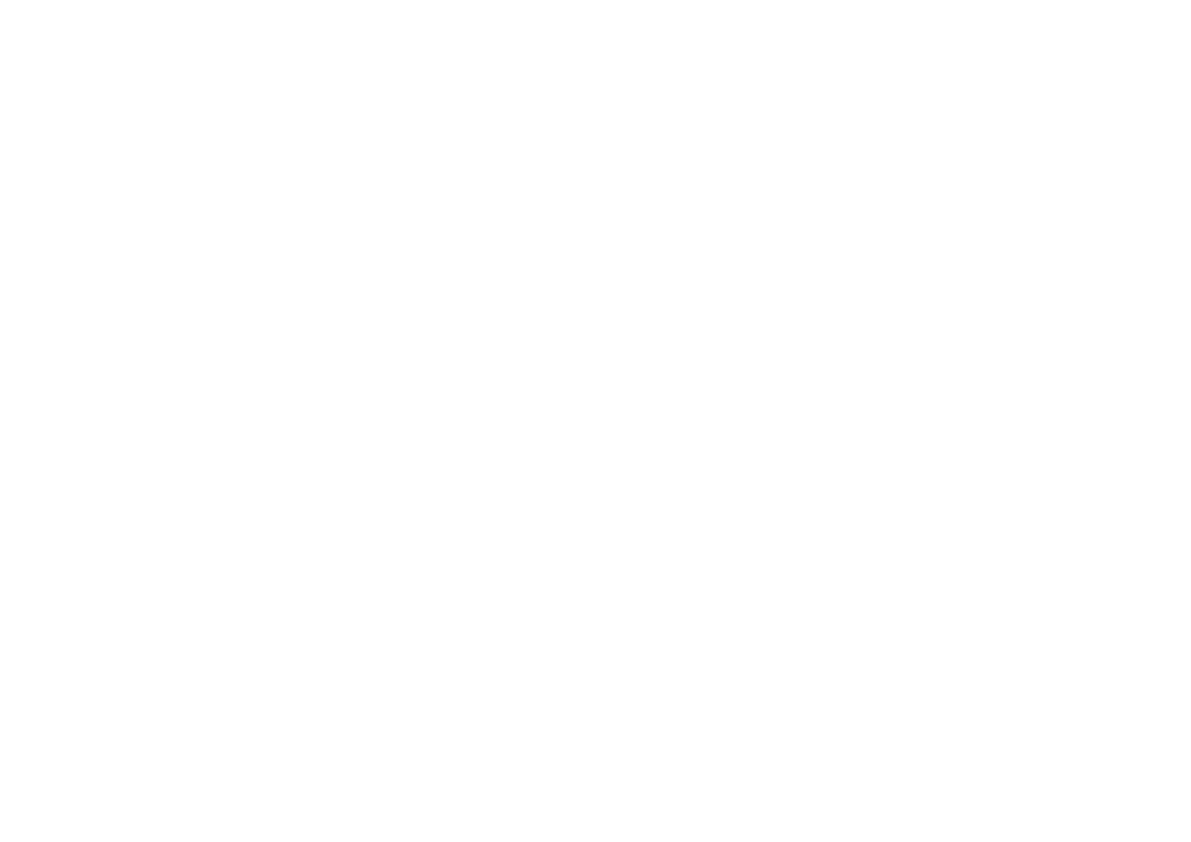近年、スマホの普及に伴って急激に増加しているビジネスモデルである「サブスクリプション(定期購入)」ですが、実は事業に乗り出したものの収支が合わず撤退するというケースが多く存在します。完全に新規の商品が市場から撤退する事はよくありますが、すでに売れていた商品のサブスク版が失敗するケースがあるのはなぜなのでしょうか。商品は欲しいけどサブスクは嫌だという消費者がいる理由を、消費者の気持ちになって考えてみたいと思います。

サブスクの定義とパターン
サブスクとは「毎月、追加の契約処理がなくても課金されるサービス」と考える事ができる。この場合、広い概念では電気やガス、従量課金サービスも含まれるが、本件ではシンプルに「決まった期間毎に定額が課金されるサービス」とし、特に物販や動画サービスを念頭に考えたいと思う。
まず、パターンとして分かりやすいのは「毎月同じ商品が届く」という定期購買型のサービスだろう。化粧品や日用雑貨、朝ごはんなど様々なサービスがこれを展開している。非常にシンプルで、事業者にも人気なジャンルだ。
次に、パーソナライズによる最適化やサプライズ商品の提供などにより、「自分で買い物するより良いものが手に入る」という品質向上型のサービスが考えられる。2000年代には商品の比較メディアが流行したが、情報に溢れかえったいま、消費者は選ぶことに疲れており、自分の生活を良くしてくれる商品が自動で届く体験を求めていると言われている。
最後に、最も有名なパターンだが「使い放題になる」「利用する権利が手に入る」という会員権型のサービスが挙げられる。古くはゴルフ会員権と同じビジネスモデルだが、WEBに同期された会員権により、動画が見放題になったり、限定コンテンツを閲覧できたり、シェアリングカーが使えたりといった様々なサービスが手に入る。
消費者にとって「定期」はメリットか
ここで考えたいのが、商品の良さではなく「サブスクにすることの良さ」が備わっているかである。例えば、とても美味しいステーキがあったとして、これが毎日届くサービスは多くの方にとって胃もたれすることだろう。商品が魅力的で買いたくなる事とそれを定期便として欲しいという事は全く別物なのだ。ステーキを毎月届けたいなら、毎月ステーキが届く便益を新しく考える必要がある。
この点で、定期購買型は商材選びが難しい。大事なのは、消費者にとって「絶対に毎月同じ量を購入し、特にブランドを選ぶ必要もない」という事だ。分かりやすいのはトイレットペーパーや洗剤といった日用雑貨だろう。これらは買い物自体に楽しみを覚える人が少なく、買い物に行く事が手間としてコストになっている。この買い物コスト削減は非常に分かりやすい便益だ。もう少し高い商材では、コスメや健康食品もこのジャンルに入るが、「絶対に使う」とユーザー心理を高める点が非常に難しい。自社へのロイヤリティを本当にそこまで高めるブランド設計をしているかは自問するべきだろう。
品質向上型の場合はこの点が分かりやすい。服ではアパレルショップ店員が、コーヒーなら喫茶店のマスターがこれまで選んでくれていた商材をWEBの力で代替するため、非常に設計が容易と言える。ただ、気を付けたいのがユーザーが本当に品質向上を求めており、かつ、それを体感できるかという点だ。お酒であれば、実は美味しいカクテルを作る能力よりバーテンダーの話術が大事という話がある。この場合、カクテルを配合するサービスはなかなか勝つのが難しいだろう。また、カクテルの美味しさというものは、よほどこだわった消費者でなければ違いに気付けない。店舗では雰囲気や話術で品質を「誤認」させるテクニックがあるのだ。
最後に会員権型では、これといった注意点は必要ないだろう。ビジネスモデルとして定期契約である事が自然だからだ。ただ、それだけにビジネス設計は難しく、使い放題モデルであれば安くコンテンツを仕入れてくる事が重要になるし、オンラインサロンなどであれば場の魅力を如何に作り込むかが重要になる。定期である点を注意する必要はないが、根本的に非常に難しいビジネスなのだ。音楽や映画がすでにサブスク化されているが、他に新しい市場を見つける選定眼とコンテンツを仕入れる交渉力があれば必ず成功するだろう。

「定期便をどうぞ」という売り方
さて、ここまで読んできて、消費者の目線に立った時、あなたの企画するサブスク商品は必ず欲しいものだろうか。もし、少しでも疑念が入る際には消費者にもそれは見透かされてしまう。「定期便でもどうぞ」という文言は、単なるアップセル導線にしか見えず、うるさく営業してくる店員のように感じられる事だろう。
特に、ユーザーが気にするのが使いきれないという問題だ。サブスクビジネスが登場してしばらく経つが、すでに多くのユーザーが届いた商品がどんどん余っていくという経験をしていると考えられる。この消費者の心理を想定せず、定期便を勧めるのはあまり優しい営業とは言えないだろう。また、合わない商品であった場合には強制的に3ヶ月も使わされることに忌避感を感じる方も多いと思う。この点も、同様に消費者の気持ちになる事が重要だ。
この際、2ステップマーケティングは有効な施策だ。これは、まずサンプルや格安商品を1回売って、そのユーザーリストに改めて定期便の営業をかけるというモデルである。ただ、この手法もかなり消費者には認知されてきており、「初回無料とか言ってるけど結局は営業がすごくくる」などと考えられてしまい、徐々に購入率が落ちてきているようだ。下心がある以上、見せ方を変えるだけで消費者は延々と騙せないという事だろう。
こう考えると、「絶対に使う」「サブスクにする事自体に意味がある」という場合を除いて、結局は食い物にされている印象を抱くのではないだろうか。ビジネス上は非常に収益予測がしやすく、広告費も圧縮できるサブスクではあるが、消費者フレンドリーにならない以上、ビジネスモデルは長続きしない。きちんと設計をして、消費者が「どうせ毎月お世話になるのだからサブスクの方が楽だな」と考えてくれるようなサービスインセンティブを考えたい。
「毎月買うから是非サブスクで!」と言わせたい
定期購買型では、基本的には同質化戦略をとって最低限の品質を担保できる信頼性と価格の安さを訴求できれば良い。髭剃り刃や歯ブラシを選ぶのに時間をかける人は少なく、安くてちゃんとしたものが毎月届けばそれが買い物にかける時間を削減するサービスとして成立する。また、化粧品などの場合には自社へのロイヤリティを高めるため、一種のオンラインサロンのような戦い方が必要になる。利用している事で、ユーザーが優越感や楽しさを感じられるようなプロモーション戦略を作っていく必要があるだろう。実際、LVMHの高級ブランドなどは価格に関わらず熱狂的なファンを存在させており、定期購入ではなくとも毎シーズンの購入を実現させている。
品質向上型では、購入の前後両方で消費者を唸らせる仕組みが欲しいところだ。例えば、「健康になる」といった訴求の商品があったとして、それを購入前後に自覚する事は可能だろうか。不可能である。それが可能なら、それは医薬品であり、サプリといった商材に該当しないからだ。むしろ、購入前に香りや味、色といった雰囲気で「自分に合っている」と感じさせ、購入後もアフターサポートにより「どんどん改善されている」と明確に分かる変化を常に与える必要がある。
会員権型の場合には、第一にはコスパの良さを訴求するのが普通だろう。どうせ映画を毎月借りるなら映画見放題の方が安いという訴求は自然で、ユーザーも加入してくれる確率が高い。ただし、そういったユーザーは多数ではないので、その場合にはオリジナルコンテンツの提供や付随サービスによって、「まあ入っておいた方が何かしら楽かも」程度に感じさせる仕組みを準備する。また、UXの良さも非常に求められ、「レンタル屋の方が楽」と決して思われないように、消費者がなんとなく起動してなんとなく利用できる作り込みを常に行う必要がある。
さて、多く記述してきたが広いテーマなだけに雑多な内容になってしまった。一概に全てをここで語る事は難しいが、少なくとも選ぶ商材がどの分野に属し、消費者にとって「定期にした方が得」と明確にする事は重要というのが本論の結論だ。多くの事業者が、「すでに弊社は1万人の購入者がおり、そのうち10%はファンになって定期購入してくれるだろう」といった楽観的観測でサブスクビジネスを始めている。定期購買は決して単品ビジネスの延長ではなく、新しいビジネスなのだということだけここまで読んでくれた読者には覚えておいていただきたい。ご拝読ありがとうございました。