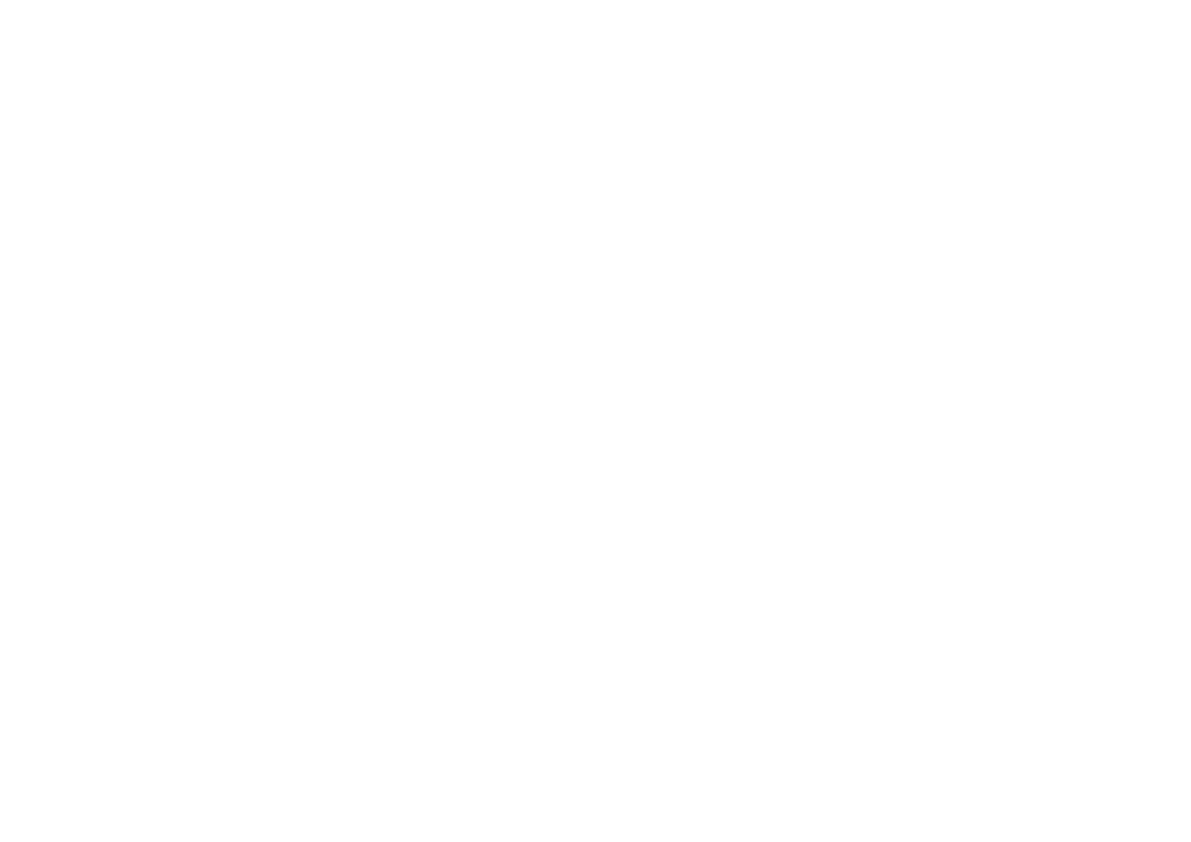販管費は企業経営において必ず発生する費用で、売上総利益から販管費を引いたものが営業利益となります。
そのため販管費の削減は、自社の利益を増やす上で重要なものです。しかし、販管費はどのようなもので、どう計算すれば良いのか分からない場合もあるでしょう。
そこでこの記事では、販管費の計算方法について解説します。
販管費とは「販売費及び一般管理費」の略称

販管費とは、企業の事業活動における商品販売や管理業務で発生した、全ての費用を足したもののことです。
会社が業務を行う上で必要となる費用から、売上原価を除いたものが販管費です。販管費が多い状態では、その分売上利益が減少してしまいます。
そのため企業が利益を伸ばす上では、以下に販管費を抑えられるかが重要なポイントです。
販売費・一般管理費の違いと勘定科目一覧

販売費と一般管理費は、企業のどのような活動から発生するかが違い、勘定科目も異なっています。
販売費・一般管理費の違いと、それぞれの勘定科目を解説していきます。
販売費は商品の販売に関して発生する費用
販売費は、商品の販売に関して発生する費用です。勘定科目は、以下の通りです。
勘定科目 | 概要 |
|---|---|
給与・賞与 | 商品販売に関わる営業部門の社員への給与・賞与 |
広告宣伝費 | 広告や宣伝にかかる費用 |
販売手数料 | 販売を委託している業者や販売代理店への支払い |
販売促進費 | 販売促進のために使われる費用 |
旅費交通費 | 取引先への移動のように営業活動で必要となる費用 |
接待交際費 | 取引先や関係者への接待費用や食事代など |
荷造運賃 | 商品の運送にかかる費用 |
上記のように営業スタッフの給与や委託業者への支払い、広告の出稿費用などが該当します。
その名の通り、自社の商品販売のために必要かどうかで判別できるでしょう。
一般管理費は会社の一般業務に必要な全ての費用
一般管理費は、企業経営のために必要となる全ての費用のことです。具体的な勘定科目は、以下の表のとおりです。
勘定科目 | 概要 |
|---|---|
給与賃金 | 従業員に支払う給与 |
役員報酬 | 役員が受け取る報酬 |
法定福利費 | 事業者に負担が義務付けられている福利厚生の費用 |
福利厚生費 | 健康診断や慶弔費など福利厚生の費用 |
地代家賃 | 事務所の家賃や駐車場の地代 |
水道光熱費 | 水道、ガス、電気代など |
旅費交通費 | 通勤手当や出張代など |
租税公課 | 税金や公的書類の発行手数料 |
通信費 | 電話やインターネット利用に必要な費用 |
車両費 | ガソリン代や車のメンテナンスに必要な費用 |
外注工賃 | 作業の外注によって発生した費用 |
保険料 | 会社所有物の損害保険料等 |
減価償却費 | 減価償却資産の当期計上分 |
中には「給与賃金」のように、販売費の勘定科目と重複するものもあります。販売活動に関するものか企業経営全般に関する費用かで、どちらに該当するか区別可能です。
販管費の分析に必要な「販売費比率」の計算方法

販管費の分析には「販売費比率(販売管理費比率)」をもとに行うのが一般的です。
販売費比率とは、企業の売り上げに対する販管費の割合を判断する指標となります。計算方法は以下の表にまとめた通り、計算対象によって異なります。
計算対象 | 計算式 |
|---|---|
販売費 | 販売費÷売上高×100=販売費比率 |
販管費 | 販管費÷売上高×100=販売管理費比率 |
仮に販管費が400万円で売り上げが1,000万円の場合、400万÷1,000万×100で販売管理費比は40%です。
2020年に行われた「中小企業実態基本調査」によりますと、販売管理費比率の目安は業種によって異なります。
飲食のように人件費がかかる業種は60%を超えていますが、製造・卸売業は仕入れ原価が高くなまため比率は10%台と低めです。
販売費比率もしくは販売管理費比率が高いようなら、売り上げに対して販管費が多く発生しているということになります。すなわち、効果的な経営ができておらず、販管費の削減が必要と判断できるでしょう。
販管費を削減するための分析方法

販管費が多い場合は、割合の大きい項目を分析し具体的な削減策を講じる必要があります。分析方法は、以下の通りです。
当期のデータから割合の大きい勘定科目を見つける
前期と当期を比較し変動の大きい勘定科目を分析する
当期のデータから割合の大きい勘定科目を見つける
ます当期のデータを分析し、割合の大きな勘定科目を見つけましょう。最も大きな割合の勘定科目は、優先的に削減すべきものです。
仮に売上高が500万円で、販管費が250万円だとします。この場合、販管費の割合は50%と、比較的高い比率です。
販管費の中にも複数の勘定科目があるため、それぞれ分解し何に最も費用が発生しているのかを分析します。
もし広告宣伝費の割合が最も大きいなら、販管費を減らすため広告宣伝費の使い方を改善する必要があるといえます。割合の大きい勘定科目が何なのかを確認し、割合の多いものから順番に削減を検討しましょう。
前期と当期を比較し変動の大きい勘定科目を分析する
前期と当期を比較し、大きく変動している勘定科目を分析するのもひとつの手です。
仮に販管費が去年と比べて10%増加しており、勘定科目ごとに分析していくと販売手数料が増えていたとします。この場合、代理店や業務委託先に支払う手数料が10%あまり増えているということです。
なぜ増加したのか、去年と何が変わったのかなどの原因を分析し販売手数料の使い方を改善することで、販管費の削減につなげられます。
また、前期と当期の変化を比較することで、翌期からの収益向上へ向けた施策を立てやすくなります。
【費用別】販管費を削減する7つの方法

ここからは、販管費を削減する7つの方法を勘定科目ごとに解説します。
役員報酬
地代家賃
人件費
旅費交通費
広告宣伝費
事務用品
通信費
勘定科目によって、削減方法は異なります。自社の販管費削減のため、参考にしてみてください。
役員報酬の削減方法
事業経営において、役員報酬が過剰になっていないか確認しましょう。見直す際は、役員報酬の変更や増減に関する規定に注意が必要です。
役員報酬は「事業年度開始から3ヵ月以内」「職制上の地位の変更があった場合」といった条件を満たさなければ変更できません。
また、毎月支払われる役員報酬は「定期同額給与(1ヵ月以下の一定期間の給与で支払額が同じ)」に該当するため、変更できるのは原則的に定期株主総会のみとなります。頻繁に変更することのないよう、慎重に決めましょう。
地代家賃の削減方法
オフィスを借りている場合、毎月の家賃も販管費の一部として発生します。事業規模に対して過剰な規模のオフィスであれば、変更を検討すると良いでしょう。スペースの無駄や立地が適したオフィスに変更することで、販管費の削減効果が期待できます。
なお、自社に適したオフィスを選ぶ際は、以下を基準にするのがおすすめです。
社員の交通費がかさむ場所ではないか
適切なスペースと空間を確保できるか
デスクやキャビネットを効果的に配置できるか
もしテレワークが可能な場合は、一部テレワークを導入しオフィスのスペースを縮小するのも有効です。
人件費の削減方法
人件費の具体的な削減方法としては、専用ソフトを導入して勤怠管理や給与計算を効率化し、業務フローの無駄をなくすのが有効です。業務の効率化・適正化を図るだけでも、人件費の削減効果は期待できます。
なお、人件費を削減する手段として、社員のリストラを行うのは避けましょう。安易なリストラは社員の反感を買い、離職につながるリスクがあるからです。
旅費交通費の削減方法
旅費交通費の削減は、規模の大きな削減対策を行わずとも実現できます。
出張の予定を把握し格安航空券や回数券を用意したり、法人プランを利用するだけでも旅費交通費を削減可能です。
また、旅行会社と法人契約し宿泊単価を下げたり、提携ホテルを利用するのもひとつの手です。現地での対面にこだわらず、Web会議を活用するのも良いでしょう。
Web会議であれば交通費や現地での宿泊代も不要となるため、旅費交通費の削減につながります。
広告宣伝費の削減方法
自社のプロモーションのために広告宣伝費を投じている場合は、定期的に見直すのがおすすめです。
いくら広告宣伝費をかけていようと、自社のマーケットやターゲットに適していなければ効果を得られません。広告宣伝を外注化している場合は、運用を任せきりになり費用対効果の問題に気づけないこともあります。
自社の広告宣伝に無駄やズレがないかを定期的に確認し、広告宣伝費を最適なものにしましょう。適切な広告宣伝費に調整することも、削減方法として有効です。
事務用品の削減方法
文房具やコピー用紙などの事務用品にかかる費用は、一つひとつの金額は少ないものの、企業規模が大きくなるほど費用がかさむポイントです。
事務用品は、ひとつの会社に決めて定期発注をかけることが多いでしょう。より安く購入できる発注先に変えるだけでも、販管費の削減効果が期待できます。
ただ、経費削減を進めることで、逆にコストが増してしまうこともあります。例えばECサイトで商品の値段を細かく確認していますと、安く購入はできますが従業員の負担が増えるでしょう。
事務用品の経費削減を推し進める際は、逆にコスト増とならないよう注意が必要です。
通信費の削減方法
通信費は比較的高額なため、見直しにより大幅な削減効果が期待できます。
自社で利用しているプランを見直したり、無駄なアプリやオプションにお金を支払ったりしていないかを確認するのも有効です。
インターネット回線によっては割引が受けられたり、法人プランによって今よりも安くなったりします。
利用するサービスや料金プランを定期的な見直しを習慣化すると良いでしょう。
販管費の計算に関するよくある質問

ここからは、販管費の計算に関するよくある質問に答えていきます。
販管費と売上原価の違いは?
人件費は売上原価になることもある?
販管費と営業利益の関係は?
販管費と売上原価の違いは?
販管費は、企業が売上をあげるため間接的にかかった費用です。一方、売上原価は商品・サービスを生み出すためにかかった費用のことで、材料費や製造部門で働く従業員の人件費などが該当します。
つまり、販管費は企業の販売活動において発生する費用で、売上原価は商品そのものを生み出すための費用という違いがあります。
企業の営業利益は「売上高ー売上原価ー販管費」の計算式で求めるため、それぞれの違いを理解していなければ業績を把握できません。
人件費は売上原価になることもある?
人件費は従業員の業務区分によって、売上原価として計上されることがあります。
たとえば、製造業の場合、工場に勤務する従業員の人件費は製造に直接関わる費用と見なされます。そのため、販管費だけではなく、売上原価にも計上される余地があるのです。
一方、本社の営業部門や管理部門で働く従業員の人件費は、販管費として見なされます。業務区分による違いには、注意が必要です。
販管費と営業利益の関係は?
売上総利益から販管費を引いたものが、営業利益となります。したがって、販管費が多ければ多いほど、営業利益の減少につながってしまいます。すなわち、販管費と営業利益は、反比例する関係にあるのです。
営業利益を増やすには、販管費をいかに削減するかが重要となります。ここまでに解説した内容をもとに、販管費の削減を目指すと良いでしょう。
販管費の計算は「SubFi for Business」で効率化できる

販管費はさまざまな勘定科目に分かれており、どの費用が多く発生しているかは企業によって異なります。
販管費の削減にあたっては、自社の経費を把握し無理なく削減できるものから少しずつ取り組んでいくと良いでしょう。
なお、販管費削減のための分析には「SubFi for Business」の活用がおすすめです。自社の経費をグラフで一目で確認できるため、販管費の分析が容易となります。
ぜひ「SubFi for Business」の導入を検討してみてください。