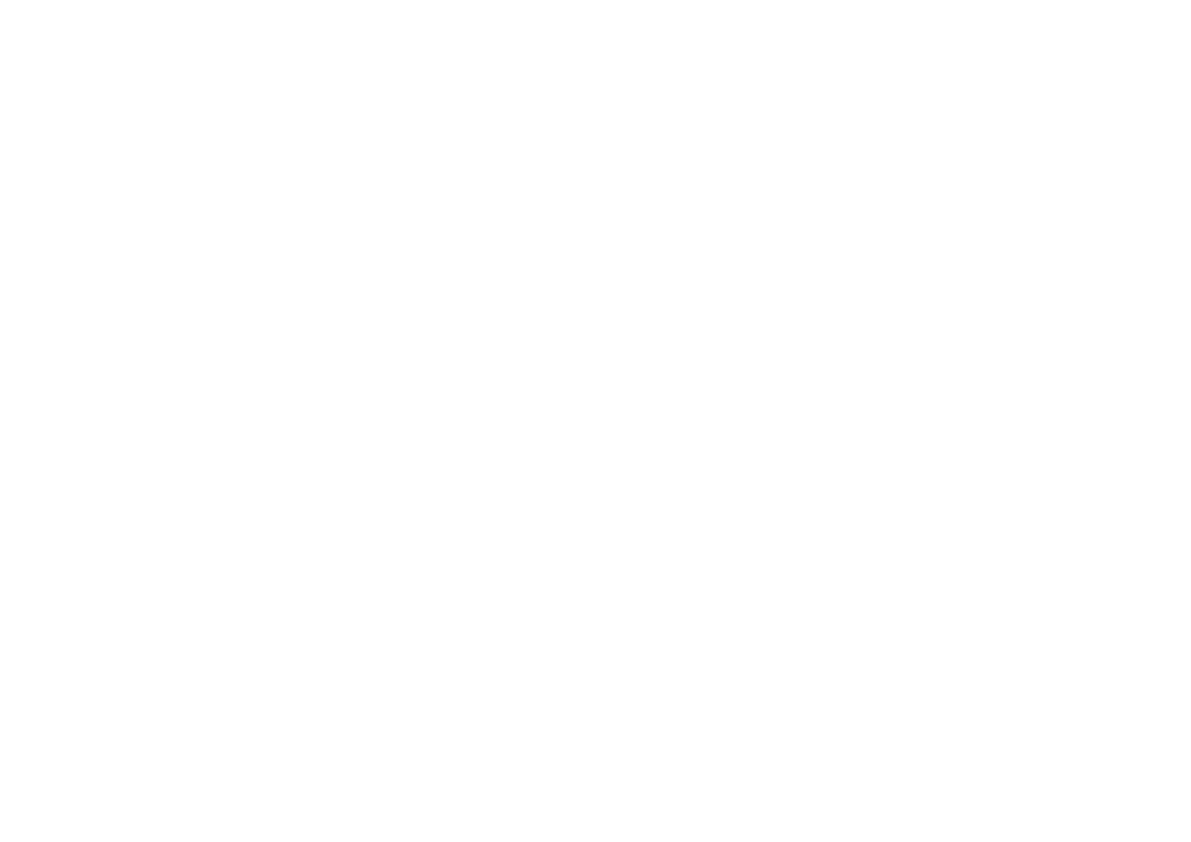経費削減に取り組みたいと考えていても、次のような悩みによって実施に踏み切れない方もいるでしょう。
「やってはいけない経費削減を行なって、会社の不利益になるのは避けたい」
経費削減には大きなメリットがある一方、間違った方法で行えば企業力の低下につながります。
こちらの記事では、経費削減で失敗しがちな施策の特徴、有能な経営者の経費削減の手法を解説します。ぜひ参考にして御社の経費削減に取り入れてみてください。
やってはいけない経費削減|5つの特徴

経費削減とは「会社の利益を最大化する取り組み」のことです。反対に「やってはいけない経費削減」は、企業力低下や減益につながる施策のことをいいます。
「やってはいけない経費削減」には、次のような特徴があります。
小さな節約のために時間コストをかける
過剰な節電を強いる
必要な人員を削減する
一律◯%のような目標を立てる
付加価値活動にかかる経費を削減する
それぞれ詳しく解説します。「経費削減の考え方」について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
1. 小さな節約のために時間コストをかける
わずかな節約のために、業務時間が増えてしまうような経費削減はやってはいけません。
たとえば、裏紙をカットしメモ用紙として再利用したとしても、節約できるのは数百円でしょう。今やメモ用紙は100円ショップで購入が可能です。
わずかな節約ができたとしても、裏紙をメモ用紙に製本するのに1時間以上かかればどうでしょう。社員の時給と照らし合わせても、賢い経費削減とはいえません。
経費削減を失敗しないためには、費用を抑えるだけでなく「時間コスト」への考慮も必要です。
2. 過剰な節電を強いる
必要以上に節電を強いる経費削減も、やってはいけません。「過剰な節電」は大きな効果が期待できない上に、リスクが大きい施策だからです。
節電には明確なルールがなく、経営が苦しくなると厳しくなり、好調になるとゆるくなる傾向があります。
たとえば、厳しい夏に空調を制限したとします。過酷な勤務環境でミスが多くなり、生産性が悪化するかもしれません。経営が厳しい上に、社員のパフォーマンスまで下がれば本末転倒です。
節電を行う際は、明確なルールを決め社員の労働環境を考慮する必要があります。
3. 必要な人員を削減する
人員削減も、安易に行ってはいけない経費削減のひとつです。
当然ながら、人員を減らせば1人当たりの仕事量は増えます。給与は同じにもかかわらず仕事量だけが増えれば、次のようなリスクが起こるでしょう。
社員のモチベーションが下がる
残業代が増える
サービス残業が増える
サービス残業を強いれば、離職率が上がりかねません。社員の業務量はさらに増え悪循環へと陥ってしまいます。
人員削減を実施する際は、業務量と必要な人員のバランスを慎重に判断する必要があります。
4. 一律◯%のような目標を立てる
「一律に削減目標を決めること」もリスクの大きな施策です。
先に数値目標を決めてしまうと、目的と手段が逆になってしまう傾向があります。何もかも一律に削減して、必要な経費まで削減してしまいかねません。
「なぜその経費なのか」「なぜその数値なのか」具体的な根拠を持って、削減項目や数値目標を決定することが重要です。
5. 付加価値活動にかかる経費を削減する
付加価値活動にかかる経費の削減には、減収へとつながるリスクを秘めています。
「付加価値活動」とは、仕入れや原材料費、顧客との商談にかかる費用など顧客満足に直接影響する業務のことです。
対して「非付加価値活動」とはやらなければならない業務ではあるものの、それ自体は利益をうまない活動です。たとえば、モノの運搬や書類の作成、会議などが当てはまります。
付加価値活動は企業経営において「かけるべき経費」であり、削減すると顧客満足度の低下につながりかねません。
削減項目を決定する際には、付加価値活動に当たらないか慎重に吟味する必要があります。
有能な経営者の経費削減|4つの手法

ここでは、有能な経営者が行う経費削減の手法を紹介します。
損益計算書の下から経費削減をする
不要な経費を見える化する
経費と時間のどちらも削減する
経営状態が良いときほど経費削減する
自社で行っている経費削減との差異があれば、改善を検討しましょう。
1. 損益計算書の下から経費削減をする
一流の経営者は損益計算書(PL)に並ぶ経費を下から削減しようとし、一流でない経営者は上から削減しようとします。
損益計算書における費用は、次のように並んでいます。
売上原価(仕入れ高)
人件費(給与・賞与など)
外注費
固定費(地代・光熱費)
営業外費用(支払い利息・雑損失など)
特別損失(固定資産税など)
法人税、住民税および事業税
有能な経営者ほど下の経費から削減を検討します。固定資産税や法人税を除くと、下部に位置するのは「雑損失・支払い利息」などです。
臨時的に発生する損失はリスク管理の徹底、支払利息は借入先の変更で削減が可能かもしれません。
上部に位置する「売上原価」の削減は、顧客満足度を下げるリスクがあります。人件費の削減はマンパワーの低下につながるでしょう。一流の経営者こそ、これらの削減には慎重になる傾向です。
2. 不要な経費を見える化する
有能な経営者は、直感や思いつきで経費削減を行いません。削減項目を見える化し、ターゲットを絞って施策を実施します。
たとえば、経費の総勘定元帳(すべての取引を勘定科目ごとに分類した帳簿)を打ち出して、社内の担当者にチェックしてもらう方法です。
現場の担当者が確認することで真に不要な項目が明確になり、経費削減の施策を講じやすくなります。有能な経営者は、根拠のない経費削減をやみくもに行ったりはしないのです。
3. 経費と時間のどちらも削減する
一流の経営者は、費用だけでなく時間の無駄にも目を光らせます。業務上の無駄を徹底的に省くことや、時間内に業務を終わらせることの重要性・メリットを理解しているからです。
反対に、一流でない経営者は経費を抑えることだけに注目し、次のように時間コストをかけてしまうことがあります。
外注していた経理作業の外注をストップする
社員の仕事が増える
業務時間内に終わらない
残業が増える
時間コストの無駄が増えれば、離職率アップや生産性の低下などにつながり悪循環に陥ります。有能な経営者は、経費を抑えることだけが会社のメリットではないことを熟知しているのが基本です。
4. 経営状態が良いときほど経費削減する
有能な経営者は、経営が好調なときほど「経費削減」を推進し、不調なときは細かい「経費削減」を強いることはありません。
というのも、経営が不調なときに経費削減を推進すると、社員や会社全体にネガティブな雰囲気が蔓延し、生産性の低下につながりかねないからです。社員の不安を煽り、対外的な不審を招く可能性もあります。
経営が好調な時から経費削減をしておけば、不測のリスクに備えられます。経営に余裕があるため、さまざまな経費削減案を試して改善を繰り返しやすいのもメリットでしょう。
一流の経営者こそ、経営状態が良好な時も「無駄をなくすこと」を怠りません。
失敗を避ける経費削減の立案ステップ

段階を踏んで経費削減を立案すれば、利益の最大化や会社の成長が期待できます。
次のステップで経費削減を進めていけば、失敗を避けられるでしょう。
会社全体で削減項目を洗い出す
定量的な目標を設定する
勤務中に目標を意識できるようにする
継続的な経費削減の分析・評価を行う
ステップ1. 会社全体で削減項目を洗い出す
経費削減を成功させるためには、従業員の協力が必要不可欠。
削減項目は、会社全体で決めることをおすすめします。各部署で、次のような項目を洗い出してもらいましょう。
利益につながらない経費や業務
顧客満足度につながらない経費や業務
利益をうまない資源(スペースや物品)
アンケートや会議を実施し、洗い出した項目の中から優先順位を決定していきます。そうすることで、トップダウンでなく「全社員で取り組む課題なのだ」という意識が広がるはずです。
ステップ2. 定量的な目標を設定する
次に、定量的な目標を設定し社内で共有します。「定量的な目標」とは、目標を数値や数量に落とし込むことです。
たとえば、次のように目標を設定します。
電気代5%減
No残業デーを週に2日実施
社内文書の30%をペーパーレス化
目標が定量的でなければ、経費削減が順調に進んでいるのか評価できません。
また「明確な数値のない削減」を目標にすると、実施が極端になってしまいがちです。無理のない範囲で削減を実施するためにも、定量的な目標を設定することが重要です。
ステップ3. 勤務中に目標を意識できるようにする
具体的な削減目標を設定したら、勤務中に社員が意識できるようにしておくと良いでしょう。
No残業デーであれば、退勤時間に退社することだけが目的ではありません。効率よく仕事を進めたり、部下に与える仕事量を考慮したりなど業務プロセスを見直すのも目的の一つです。
オフィスの目立つ場所に削減目標を掲示するなど、勤務時間中に効率的な業務を意識できる工夫が必要です。
ステップ4. 継続的な経費削減の分析・評価を行う
経費削減を実施する上で、分析や評価は欠かせません。企画段階での想定通りになっているか、予測しなかった効果や影響はないか評価します。
定期的な分析・評価と改善を重ねれば、無駄のない適正な経営状態へと近づくでしょう。
経費削減の分析・評価に不安がある方には、おすすめのサービスを後ほど紹介するのでご検討ください。
リスクを避ける経費削減のアイデアとツール

経費削減を成功させれば会社の利益を最大化できますが、やり方を間違えると業績を悪化させてしまいかねません。
そこで、リスクが少ない経費削減のアイデアを4つ紹介します。
固定費の見直し
テレワークの推進
システムのデジタル化
会計管理サービスの導入
経費削減の成功事例を詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
固定費の見直し
固定費は額が大きく、変動が少ない項目です。顧客満足度には直結しないため、削減してもリスクが少ないという特徴があります。
次のような費用が固定費として挙げられます。
電気代の基本料金
インターネット通信費
コピー機などのリース料
賃料
固定費は毎月必ずかかる費用で、年間にすれば大きな額です。サービスは変わらず費用だけを抑えられれば、インパクトが大きい経費削減となります。
今まで使っていたサービスを変えて不便になるのを避けたい場合は、契約している会社と交渉するのもひとつの手です。
具体的には、複数の会社から取った見積もりをもとに、現在の会社に新たな料金プランを提案してもらうのも可能でしょう。
テレワークの推進
テレワークの推進も、リスクの少ない経費削減の手法です。
出社する従業員が減少すれば、実質的に照明や空調の使用時間を減らせます。多様な働き方にも対応でき、社員の満足度にもつながるでしょう。
他にも、本社で会議が行われているなら、支社の社員はオンライン会議も可能にします。旅費交通費の削減だけでなく、移動時間の短縮にもなります。
テレワークの推進は、経費や時間コストの削減、社員の満足度アップを同時に叶えられる施策です。
システムのデジタル化
システムのデジタル化による経費削減もリスクが少なく推奨されます。
たとえば、入出金にかかわる業務をデジタル化すれば、経理部門の負担を軽減できるでしょう。
システムがデジタル化すれば、紙にプリントアウトする機会が少なくなります。ペーパーレス化も同時に促進でき、業務の効率化や消耗品費の削減が期待できるのもメリットです。
会計管理サービスの導入
経費削減を失敗に終わらせないためには、自社の収益構造の分析評価を継続して行うことが重要です。分析や評価を行わなければ、取り組んだ施策が会社の利益にどう影響したのか確認できません。
ただし、自社の収益構造をリアルタイムで評価するのは、時間やコストがかかります。
そこで推奨したいのが会計管理サービスの導入です。会計管理サービスなら、わずかな初期コストで登録したその日から利用を開始できます。
「SubFi for Business」なら収益構造をリアルタイムで把握できる

「経費削減を実施したいが、失敗を避けたい」とお考えなら、コスト構造をリアルタイムで把握できる「SubFi for Business」がおすすめです。
部門や事業ごとに分散した会計データを雑多なまま取り込んでも、自動で「事業に必要な支出」のみを抽出します。さらに、AIが同業他社などの財務状況をもとに最適なコスト削減プランを提案してくれます。
経費削減について不安がある方は、コスト管理スペシャリストへ直接質問することも可能です。ぜひ「SubFi for Business」をご検討ください。