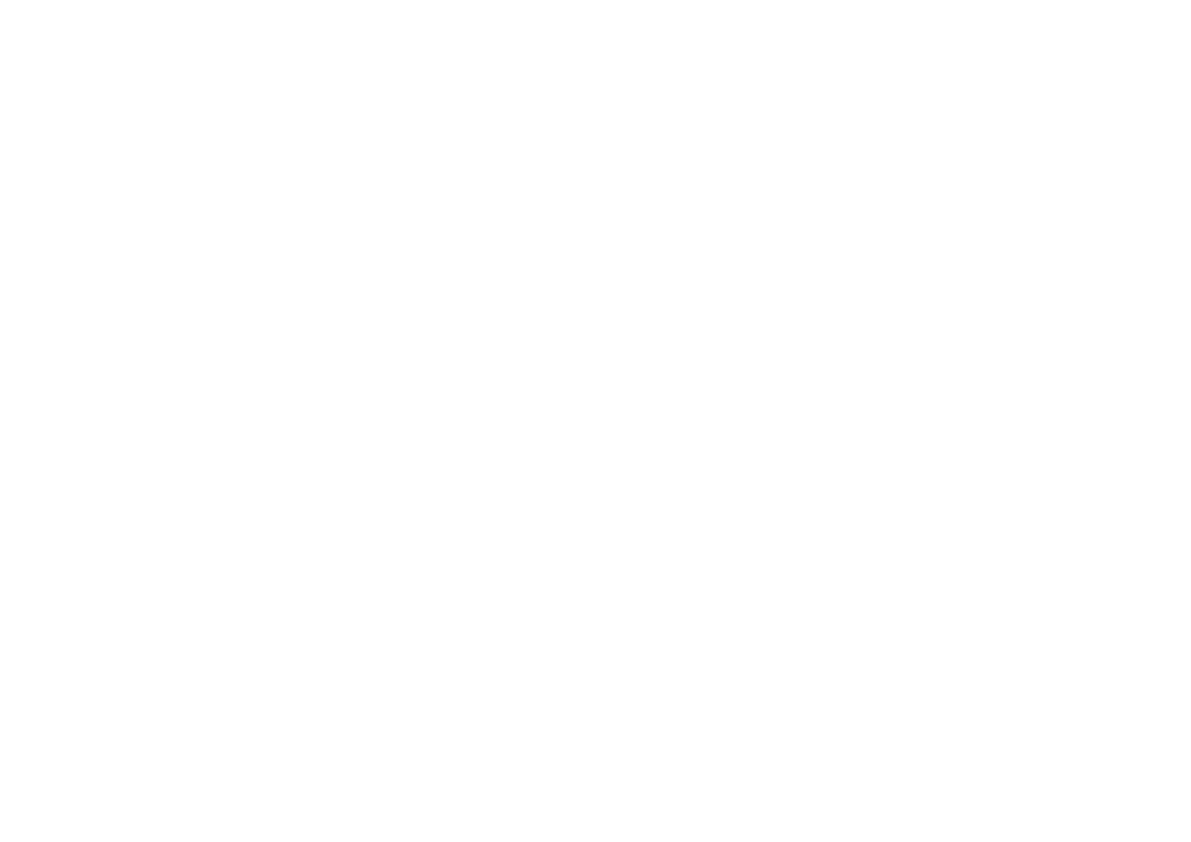製品やサービスには、必ず競合となる企業が存在しますが、ただ他社との違いを知っていれば良いというわけではありません。
状況を把握し、戦略を立てることが重要であり、そのためには競合分析が必要不可欠となります。
しかし、競合分析という言葉は知っていても、詳細が分からないことから、以下のような疑問をお持ちではないでしょうか。
そもそも競合分析とは何のために行うのか
競合分析を行う手順は
競合分析を成功させるポイントとは
本記事では、競合分析の手順や効果的なフレームワーク、競合分析を成功させるためのポイントなどを解説します。初心者にも分かりやすいように例も交えているので、ぜひ参考にしてください。
競合分析とは

競合分析とは、顧客が自社以外に選ぶ可能性がある企業を分析して、事業戦略に役立てる手法です。競合分析を行うことで、自社の強みや弱みを明確にし、市場全体を可視化することが可能となります。
分析を行う際は、自社の中だけで競合設定・分析を行うのではなく、顧客視点から進めるのが基本です。正しい目線を持つことで分析結果の信ぴょう性が高まるため、しっかり把握しておきましょう。
競合分析の目的
競合分析は、分析結果や得られた情報を何のために使うのか明確にする必要があります。
自社の市場競争力を把握するため
自社の強みや弱みを洗い出すため
商品やサービスの開発や改善のため
戦略立案のため
企業によって求める目的はさまざまであり、競合分析はその目的を達成するための最も効果的な手法の1つです。目的への意識が薄れないよう注意し、きちんと戦略につなげるようにしましょう。
競合分析でカバーすべき範囲
競合分析でカバーすべき範囲は、業界やビジネスの種類、何を戦略に生かしたいのかによっても異なります。一般的な項目については以下の通りです。
製品やサービスの特徴
顧客層
マーケティング戦略
ビジネスモデル
将来の展望
制作コンテンツ
業績
強みや弱み
範囲を広げすぎると膨大な手間やコストがかかるため、目的を明確にし、戦略に活かしたい項目だけに絞った方が良いでしょう。
その中で、なぜ見込み客から自社が選ばれるのか、選ばれ続けるためにはどうするのかを見極める必要があります。
競合分析に使用するフレームワーク4つ

フレームワークとは、物事を枠組に合わせて分類していく作業を指します。事業の戦略構築に関わる競合分析と組み合わせることで、より有益な情報が得られるでしょう。
ここでは、一般的に活用されている以下4つのフレームワークを解説するので、ぜひ参考にしてください。
3C分析
4C分析
4P分析
SWOT分析
3C分析
3C分析は、Customer(市場・顧客)・Competitor(他社)・Company(自社)といった「3つのC」をベースに分析を行います。
3つのC | 分類例 |
Customer | 顧客の年齢層や価値観、市場のトレンドなど |
Competitor | 競合他社の情報や動向など |
Company | 自社で扱う製品やサービス、経営状況など |
上記のように分類し、市場・顧客・他社の状況を把握しながら次の事業戦略を考えるのが3C分析です。
4C分析
4C分析は、Customer Value(顧客にとっての価値)・Customer Cost(顧客が費やすお金)・Convenience(顧客にとっての利便性)・Communication(顧客とのコミュニケーション)の「4つのC」で構成されています。
消費者側の視点でマーケティングを見つける手法であり、以下のように状況を分類します。
4つのC | 分類例 |
Customer Value | ・製品を求める顧客の属性から、真に求められている機能性や価値など |
Customer Cost | 製品の価格や、付随する心理的、生産的コストなど |
Convenience | ・実店舗:アクセスや営業時間など |
Communication | ホームページやSNSなどの情報発信手段 |
上記のように4つに分類すれば、顧客にとっての価値・コスト・利便性・コミュニケーションの状況を正確に把握できるでしょう。
製品・サービスを販売するために、消費者側の視点でマーケティング戦略を考えたい企業におすすめです。
4P分析
4P分析はProduct(製品)・Price(価格)・Place(流通)・Promotion(プロモーション・販売促進)の「4つのP」で構成されています。
以下のように状況を分類し、企業側の視点でマーケティングを見つける手法です。
4つのP | 分類例 |
Product | 自社の製品 |
Price | 価格 |
Place | 製品を売るための店舗など |
Promotion | CMや広告、キャンペーンなどの販売促進 |
4P分析は製品・価格・流通・販売促進などの状況を把握し、企業側の視点からマーケティング戦略を考えられます。そのため、先ほど触れた4C分析と組み合わせれば、より隙のない分析につながるでしょう。
SWOT分析
SWOT分析はStrength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)といった4つの要素から状況を可視化します。
4つの要素 | 分類例 |
Strength | 自社の強みなどの内部環境(ポジティブな要素) |
Weakness | 自社の弱みなどの内部環境 |
Opportunity | 新しいサービスなどの外部環境(ポジティブな要素) |
Threat | 新型コロナウイルスによる影響などの外部環境 |
SWOTごとに分類することで、強み・弱み・機会・脅威などが把握できるため、うまく活用すれば自社が勝負をかけるポイントを見極められるでしょう。
競合分析のステップ8つ手順

競合分析を行うには、きちんとした手順を踏まなければなりません。
実際に着手する前に、ここから解説する8つのステップを確認しておきましょう。
ステップ1:分析すべき競合企業の特定
競合分析を行う際は、まず競合企業を特定しなければなりません。
参考までに、競合とは顧客への提供価値を争う企業を指し、顧客が「何かを欲しい」「買いたい」と考えたときに、頭に浮かんだ自社以外の選択肢が競合にあたります。
ただし、競合を決めるのはあくまでも消費者となるため、消費者の目線に立って設定を行いましょう。
ステップ2:競合他社の情報を一覧にまとめる
業界や市場を調査し、類似する商品やサービスを提供する企業をリストアップしましょう。その際、突然細かく比較する必要はありません。
競合他社の弱み・強み・特徴・セグメント別の売上などをホームページなどから情報収集し、できるだけ多くを一覧に列挙するのがおすすめです。
全体を把握することで、競合企業の戦略やビジネスモデルの理解につながり、自社の強みと弱みも明確にできるでしょう。
ステップ3:競合他社の商品・サービス分析
競合他社が提供する商品やサービスの品質・価格・機能・特徴・顧客満足度などを分析することで、他社の強みと弱みを分析できます。
具体的には、自社と他社のサービスを比較して相対的な優位性を顧客目線で見つけ、提供価値やベネフィットなどを明確にする形です。
その際、「顧客にとっての価値」は特に深く掘り下げ、なぜ自社が選ばれるのか明確な仮説を立てられるようにしましょう。
ステップ4:競合他社のマーケティング戦略分析
次に、競合他社が使用しているプロモーション戦略や販売チャネルといった、マーケティング戦略を分析します。
広告ビジュアルやキャンペーン方法、販売しているエリアなど、自社のビジネスに関連しそうな項目を選び、一覧化する流れです。
最後に自社と比較することで、マーケティング戦略の課題点などが浮き彫りになるため、丁寧に取り組んでみてください。
ステップ5:自社と競合他社の比較
このステップでは、市場競争力を向上させるために自社と競合他社を総合的に比較していきます。
商品やサービス・価格・販売チャネルといった項目を調査し、マッピングすることで市場全体の構図を資格的に理解しやすくなるでしょう。
その際、自社の売りやこだわりばかりを列挙するのではなく、顧客視点で選ばれるポイントを定量的に判断することが重要です。
ステップ6:必要に応じて市場調査を実施する
ステップ5までは、インターネットの情報などをもとに調査する方法を紹介しました。
しかし、それだけでは情報が十分とは言えないため、必要に応じて以下のような市場調査を実施しましょう。
顧客へのアンケート調査
WebやSNS調査
購買データ分析
ミステリーショッパー
市場調査によって、競合他社の製品やサービスの特徴、販売戦略などがより明確に把握でき、効果的な戦略立案が可能となります。
ステップ7:自社の戦略を検討する
これまでの分析結果をまとめ、競合企業と自社を比較した結果をもとに、自社の戦略を再評価して改善点などを見つけましょう。
実際のところ、キレイに情報をまとめることに満足して、戦略立案をおざなりにしてしまうケースも少なくありません。しかし、競合分析の根本的な目的は集めた情報をもとに効果的な戦略を立案することです。
自社の弱みや強みを明確にし、製品やサービスの改善や目指すべきポジショニングなどを検討しましょう。
ステップ8:戦略を実施する
戦略を立案した後は、最終的なゴールに向けて実行に移しましょう。
ただし、一度で成功するケースは稀であり、基本的にはトライ&エラーを繰り返して微調整していくことになります。
運用する中で生まれた改善点などを細かくリストアップし、商品やサービス、マーケティング戦略を定期的に見直してみてください。
競合分析を成功させるためのポイント

競合分析を実施するだけでは、求める成果を得ることはできません。分析で知った情報を活かしつつ、適切な分析を追加で行い、自社の戦略立案に役立てることが重要です。
そこでここでは、競合分析を戦略立案に役立て、最終的な目的を達成するためのポイントを紹介します。
定期的に競合分析を実施する
競争環境や市場は常に変化するため、初回の競合分析だけでは、自社の売上アップや認知度向上につながりません。
競合分析は戦略実行後も定期的に行うことが大切であり、タイムリーな情報を落とし込むことで効果が最大化されます。
その際、自社の戦略を必要に応じてアップデートすれば、より効率的に他社と差別化できるでしょう。
目的を明確にする
自社のコスト戦略や商品の改善、新しいビジネスアイデアなど、競合分析を行うゴールを明確にすることも重要です。
目的を明確にせず競合分析を行ってしまうと、必要のないデータも集まり、作業効率が低下する可能性があります。分析の精度を高める上でも大切なポイントなので、しっかり押さえておいてください。
市場変動に対する柔軟な戦略の構築
事業を展開するときに、市場や顧客ニーズの変化の早さに苦戦する企業は少なくありません。
トレンドについていけなければ、早い段階で競合他社に追い抜かれ、見込み客のニーズも捉え切れなくなってしまいます。そのため、最初の競合分析で終わりではなく、発見した違いや状況を活かして、どのようにポジショニングをするかを考え続けましょう。
ただし、データ収集や分析などに時間を取られすぎて、緻密に設定した戦略を実施するまでに時間がかかりすぎてしまうこともあります。
最悪の場合、戦略を実施するころには、顧客のニーズが変わってしまっていることも考えられるので、スピーディーかつ柔軟に対応できる体制を整えておくことが重要です。
「SubFi for Business」で効率的に戦略を立てよう

競合分析は、競合他社の製品やサービス、価格戦略などを分析し、自社の市場競争力を把握するための重要な施策です。
しかし、ただ競合他社の情報や自社の状況を分析するだけでは、競合分析の本来の成果を得ることはできません。顧客の分布を理解し、自社のターゲットを定め、競合との違いを明確にする必要があります。
ただし、社内リソースだけで競合分析を行うと、本業に支障がでたり、間違った解釈で進めてしまうリスクもあるでしょう。
そこでおすすめなのが、「SubFi for Business」です。ベンチマーク業界の規模や出店予定地の投資基準などを簡単に参照可能であり、競合他社の支出平均、人気のITツールなども確認できるため、リソースを節約して効率的に戦略を立案していけるでしょう。
「コスト分析に悩んでいる」「競合分析がよくわからない」と悩んでいる方は、ぜひSubFi for Businessを検討してみてください。
株式会社koujitsuの競合分析に関する記事はこちら↓
なぜ競合他社分析がビジネス成功に不可欠なのか?