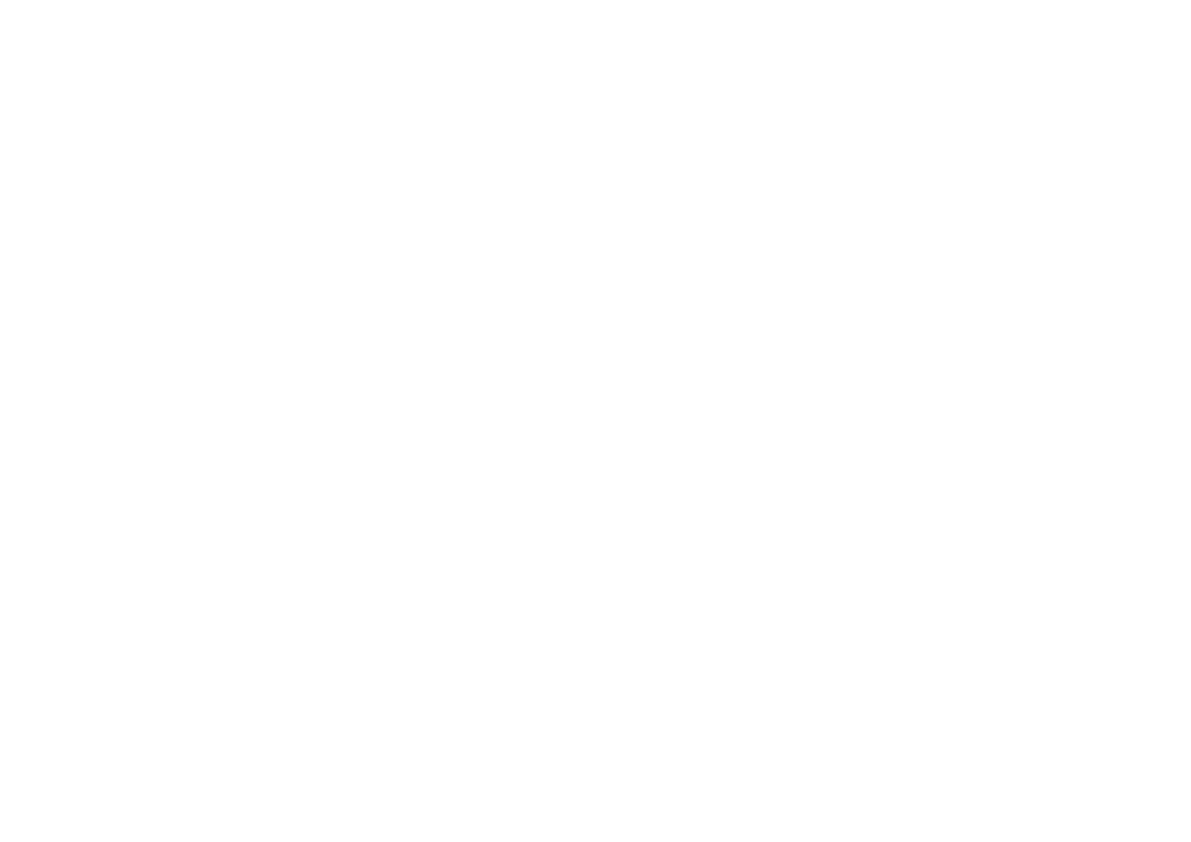企業経営において、販管費率の分析は非常に重要です。売上に対する費用発生を示す数字であり、売上に対する効率性の度合いがわかります。
しかし、売上原価の計算とは違い、何を目安にすれば良いのかわからないと感じる人もいるでしょう。販管費率を分析するには、業種や企業規模の目安が必要です。
こちらの記事では、業種別・企業規模別の販管費率の平均や分析の際のポイントを紹介します。時差の販管費率を把握や分析により、無駄なコストを削減でき企業成長も見込めます。ぜひ参考にしてください。
販管費率とは|売上高に占める販管費の割合のこと

販管費率は、売上高に対して「販管費(販売費+一般管理費)」が占める比率のことです。
次のような言い方をすることもあります。
SGA Ratio(英称)
売上高販管費率
販売管理費率
販管費率の数値によって、商品・サービスを販売するのにどれだけ費用がかかっているか「効率の良さ」を測れます。
販管費とは|販売費+一般管理費

販管費とは「販売費」と「一般管理費」を足し上げた費用のことです。簡単にいうと、売上原価を含まない、すべての費用をいいます。
販管費は次の2つに分類されます。
販売費
一般管理費
それぞれ詳しく説明します。
販売費|販売に直接かかわる費用
「販売費」とは売り上げに直接関わる費用のことで、売上に関連して変動するのが通常です。
たとえば、ひとつの商品を販売する場合には、次のような費用が「販売費」となるでしょう。
内容 | 勘定項目 |
|---|---|
宣伝にかけた費用 | 広告費 |
販売のために動いたスタッフ | 人件費 |
商品の配送料・配送手数料 | 運賃 |
企業によっては、販売費のことを「販売管理費」「営業経費」などと言うこともあります。
一般管理費|事業を維持管理する費用
一般管理費とは、売り上げとは直接関わりなく事業の経営維持のために必要な費用全般をいいます。
一般管理費は「固定費」であることが多く、具体的な勘定項目は次のとおりです。
人件費
旅費交通費
光熱費
消耗品
減価償却費など
基本的に一般管理費には「固定費」が多く、変動するのは稀です。
「人件費」は売上原価とすることもある
「人件費」を売上原価と捉える企業や業種もあります。その場合の人件費は「販管費」に含まれないため注意が必要です。
とくに、次の業種では、人件費を「売上原価」と捉える場合があります。売り上げに対して直接的に発生する費用と考えるためです。
製造業
サービス業など
他社との販管費率を比較する際は、「人件費をどの項目に含んでいる」かの確認も必要でしょう。
販管費率の計算方法

販管費率は、次の計算式に当てはめると簡単に求められます。
売上高販管費率(%) = 販管費(販売費+一般管理費) ÷ 売上高✖️100
「売上原価」を含まないすべての経費の割合を「販管費率」として計算します。
計算する際の詳しい勘定項目を詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
販管費率の考え方

販管費率は、上記の計算によって簡単に導き出されます。計算して終わりではなく、数値をどのように考えるかがポイントとなります。
販管費率の考え方は次のとおりです。
販管費率は低いほど営業効率が良い
企業の戦略・成長フェーズによって変化する
業種や規模によって目安は異なる
販管費率は低いほど営業効率が良い
一般的に、販管費率の数値は低いほうが好ましいと考えられます。売上に対する販売費および一般管理費の少なさは、営業効率の良さを示しているためです。
たとえば、売上高が同じA社とB社を比べるとわかりやすいでしょう。
A社:1000万円の売上に対して、販管費が200万円
200万円÷1000万円×100=20%(販管費率)
B社:1000万円の売上に対して、販管費が300万円
300万円÷1000万円×100=30%(販管費率)
少ない費用で効率良く売上を立てているA社は、低い販管費率になっています。
つまり、販管費率を分析する際は「競合他社より低い数値か」「過去の数値より低くなっているか」がポイントです。
ただし単純に「販管費率の数値は低ければ良い」と判断できない場合もあるため注意しましょう。詳しくは次に説明します。
企業の戦略や成長フェーズによって変化する
必ずしも「販管費率が高くなる=NG」とは言い切れません。
販管費に含まれる「販売費」は「戦略費」とも呼ばれており、企業の戦略方針によって大きく増減します。つまり、販売費が大きくなるフェーズでは必然的に販管費率の数値も高くなるのです。
たとえば、次のようなシーンでは「販売費」が大きくなるでしょう。
新商品開発のための研究費がかかる
新規サービス立ち上げの広告費や人件費がかかる
将来性のあるサービスへ投資をする
上記のように、広告宣伝に力を入れるべきと判断した時期なら、販売費は大きくなり販管費率の数値も上がります。
販管費率を経営に活かすためには、背景にあるビジネスの実態まで読み解くことが重要です。
業種や規模によって目安は異なる
他社の販管費率と比較する際に、注目すべきポイントは「業種」と「企業規模」です。
販売管理費は売上原価を計算に含まないため、業種が違えば前提条件も異なります。
たとえば、商品や材料の仕入れによって売上を立てている「小売業」や「製造業」の販管費率は、低い傾向です。対して、人件費や維持費に比重がかかる「サービス業」の販管費率は高くなります。
また、従業員規模の大きい企業では業務効率がしやすいため、販管費率は低くなりがちです。
販管費率を比較する場合は「同じ業種」「同程度の企業規模」の会社を選ぶようにしましょう。
販管費率の目安

販管費率を分析するために、基準とする目安を知りたいという人もいるでしょう。参考にするなら「業種」や「事業者規模」別での平均目安を見ていくのがおすすめです。
こちらでは経済産業省が2022年に調査した「中小企業実態調査」より、次の目安をご紹介します。
全業種の平均目安
業種別ランキング
企業規模別の平均目安
全体の目安は約23%
経済産業省が2022年に177万の企業を調査した「中小企業実態調査」によると、販管費率の平均は23.7%です。多少の変化はあるものの、どの年も20%前後を保っています。
ただし、企業規模や業種によって販管費率は大きく異なります。次に業種別、企業別の販管費率の目安を紹介するので参考にしてください。
参照元:e-Start 政府統計の総合窓口
業種別ランキング
次の表は、2022年に調査した「中小企業実態基本調査」から産業別に販管費率を求め、低い順に並べたものです。
業種 | 販管費率 | |
|---|---|---|
1 | 卸売業 | 13.9% |
2 | 製造業 | 17.6% |
3 | 建設業 | 19.4% |
4 | 運輸業,郵便業 | 23.9% |
5 | 小売業 | 28.9% |
6 | 不動産業,物品賃貸業 | 31.4% |
7 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 37.5% |
8 | 情報通信業 | 40.9% |
9 | サービス業(他に分類されないもの) | 41.9% |
10 | 学術研究,専門・技術サービス業 | 43.0% |
11 | 宿泊業,飲食サービス業 | 76.2% |
合計平均 | 23.7% |
販管費は「売上原価を含まない」ため、業種によって販管費率の差が大きくなっています。
ホテルやサービス業は、売上原価への比重が少ないため、販管費率が高くなる傾向です。対して、卸売業や製造業は、売上原価への比重が多く、販管費が少ないため販管費率は低くなります。
製造業は平均に比べて低い比率ですが、実際には衣料品と重工業で全く異なる比率になるため一概には言えません。多くの場合で、製造と販売、在庫管理などを紐づけることで自社の販管費を正しく把握し、コスト削減の余地を見つけられる様になります。製造業における販管費の把握については以下の記事が販売管理システムとして詳しく紹介を行なっています。
https://techsuite.biz/manufacturing-sales-management/
企業規模別の平均目安
同じく経済産業省の2022年のデータから、企業規模別の販管費率を計算し表にしたものを紹介します。
法人企業の従業員数 | 販管費率 |
|---|---|
51人以上 | 19.6% |
21~50人 | 22.2% |
6~20人 | 25.7% |
5人以下 | 30.0% |
合計平均 | 23.1 % |
個人企業 | 38.1% |
|---|
従業員規模が大きい企業ほど、販管費率は低くなっているのがわかります。
合計平均は約23%ですから、従業員数21〜50人の会社規模であれば業種別の販管費率をそのまま目安にすれば良いでしょう。
業種と従業員規模を組み合わせると、平均販管費率の考え方は次のようになります。
自社の業種の平均値(例:製造業なら17.6%)
従業員数が21〜50人規模より大きいか小さいか
大きければ業種の平均値より低く見積もる
小さければ業種の平均値より高く見積もる
たとえば、製造業で従業員が15人なら、販管費率の目安は17.6%よりも高い数値を目安にすると良いでしょう。
企業経営に活かす分析ポイント5つ

販管費率を求めるのは簡単ですが、企業成長につなげるにはポイントを押さえた活用が大切です。
次の5つのポイントを紹介します。
同業種・同規模の企業と比較する
販管費のすべての項目を分解する
販管費率の推移表を作成する
削減できる項目はないか検討する
会計管理サービスを導入する
①:同業種・同規模の企業と比較する
販管費率の分析には「他社との比較」「自社比較」が必要です。
「他社との比較」で押さえておきたいのは、同じ業種・規模の企業との比較です。前提条件が異なる比較では、参考になることはあっても自社の経営に取り入れるのは難しいでしょう。
次のように、業種によって経費の比重が異なり販管費率にも差が出ます。
【販管費率が低い】
売上原価(仕入れ・材料費など)が多くを占める業種:製造業・卸売業など
【販管費率が高い】
一般管理費(人件費・光熱費など)が多くを占める業種:サービス業・宿泊業など
規模別では、企業規模が大きくなるにつれて販管費率が下がります。業務効率化には規模的な要素が関わってくるためです。
他社の販管費率を参考にする場合は、「同業種か」「同規模か」を確認するようにしましょう。
②:販管費のすべての項目を分解する
販管費率から多くの情報を得るには、中身を分解して考えるのが有効です。
次のような構成要素が含まれるため、それぞれ分けて考えます。
人件費
賃料
配送費
交際費
減価償却費
広告宣伝費
研究開発費
それぞれの項目を分解した上で、次の点について検討してみましょう。
どの項目が、販管費の比重を占めているか
戦略的(意図的)な数値か
削減の余地はあるか
このように販管費を分解してみると、経営状況の分析や改善点の洗い出しが容易になります。
③:販管費率の推移表を作成する
販管費率の分析には「自社比較」が重要です。過去実績と比較するには、月単位の販管費率を記した推移表の作成が有効です。
さらに詳細な分析には、次の2点も加えると良いでしょう。
販管費にそれぞれの要素が占める割合を見る
要素別の推移表を作成する
推移表の作成は、想定外の経費の動きや要因に気づきやすくなるのがメリットです。
④:削減できる経費はないか検討する
推移表を作成し、次のような傾向が見られたら「経費削減」を検討しましょう。
想定以上に販管費率が上がっている
一般管理費の要素で、とくに増加した項目がある
企業戦略により「販売費」が一時的に高まることがあります。戦略的に広告や販促に費用を投下している場合は「販管費の増加が想定の範囲内か」「売上への貢献度はどの程度か」など状況を追っていく必要があります。
一方、企業の業務管理に関わる「一般管理費」に、大きな変動は考えにくいものです。
経費削減は「一般管理費」から考えていくのが有効です。直接売上に関わる費用ではなく固定費であることが多いため、インパクトのある経費削減ができます。
企業成長につながる経費削減について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
⑤:会計管理サービスを導入する
販管費率を企業経営に活かすには、会計管理サービスを導入するのも一つの方法です。
販管費率を分析すれば「どれほど効率よく売上を立てているか」といった営業効率を可視化できます。経営改善のヒントにもなるため、販管費率の把握は企業経営には欠かせません。
しかし、販管費の項目分析や同業他社の調査には、手間や費用がかかります。
会計管理サービスを導入すれば、少ない費用で始められ、販管費率の詳細な分析も可能です。バックオフィスを追加したり、人件費を投入したりする必要もありません。
販管費率をリアルタイムで把握するなら「SubFi for Business」

「販管費率が大切とはわかっていても、細かく分析する時間がない」「競合他社との比較をどのように経営に活かせば良いかわからない」という人は「SubFi for Business」がおすすめです。
「SubFi for Business」は、支出をキャッシュフロー基準に一元管理できるサービスです。同業他社の課目別の支出割合が確認でき、AIが財務分析を行いどのようにコストカットするかも提案してくれます。
部門や事業ごとに分散した会計データを雑多なまま取り込んでも、自動で「事業に必要な支出」のみを抽出するため、時間や手間をかけません。
販管費率をうまく経営へ活かせるか不安な方は、コンサルタントへ直接質問することも可能です。ぜひ「SubFi for Business」をご検討ください。