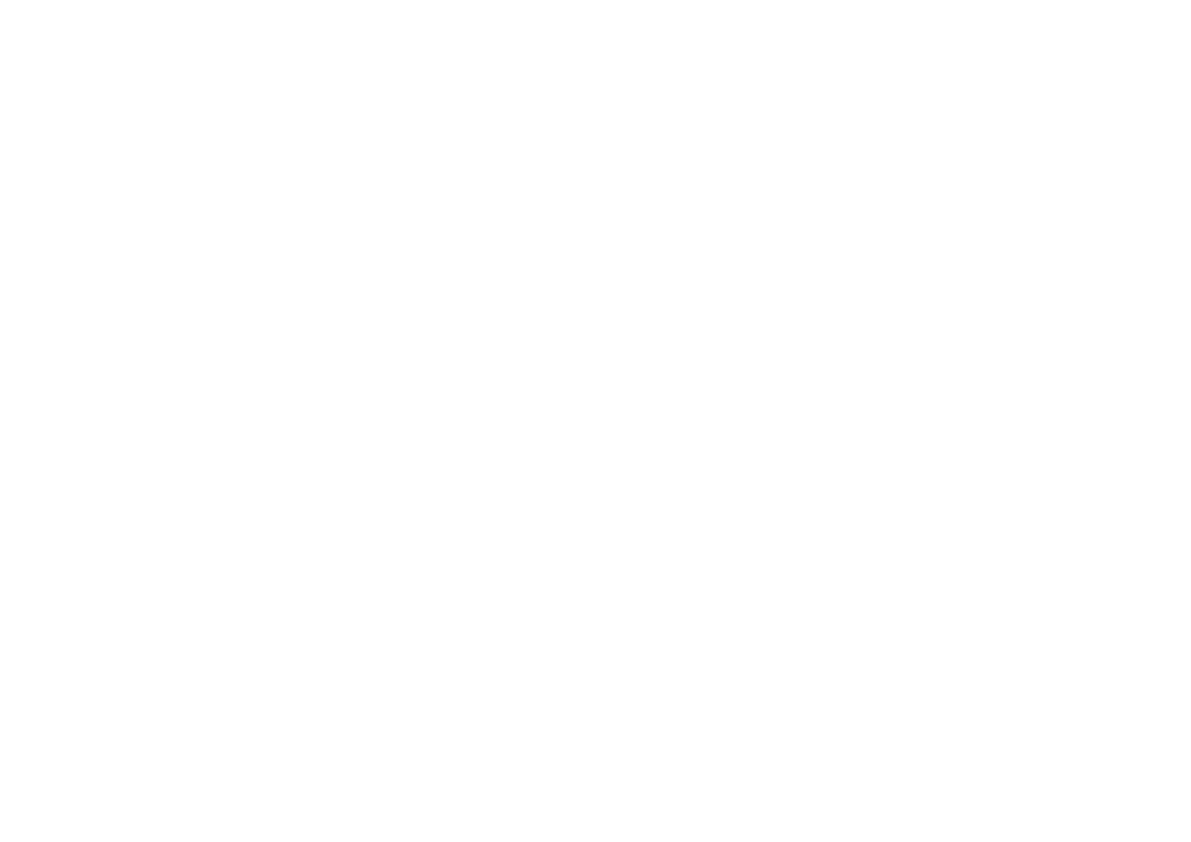経営赤字を継続すると企業の信用低下を招き、資金調達の難化や取引先との信頼関係の悪化などを引き起こす可能性があります。
しかし、すべての赤字決算が経営破綻につながるわけではありません。赤字経営は衰退リスクが極めて高い経営状態ですが、黒字経営でも不健全な経営を行っていると黒字倒産につながるケースもあるのです。
そこで本記事では、経営赤字のメリット・デメリット、黒字との違いなどについて紹介します。「長期的に健康的な経営をしたい」「財務改善をしたいけど何から始めていいかわからない」などの悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
経営赤字とは

経営赤字は、売上高から仕入れ代金や人件費などの経費、借入金返済など負債を差し引いた結果、純利益がマイナスの経営状態を指します。
純利益は、企業が特定の期間内に得た利益のうち、経費や負債の支払いを差し引いた最終的な利益です。会社存続に不可欠な利益が手元に残らないため、企業の成長発展は難しいといえるでしょう。
しかし、経営赤字であっても必ずしも倒産するわけではありません。たとえば、会社経営以外からの収入源があったり、他の事業部門や部門ごとに収支のバランスが取れていたりなど企業全体の経営状態で問題ない場合があります。
ただし、いずれにしても経営赤字は企業にとって懸念すべき状況であり、赤字経営の原因を分析し収益の向上や経費削減などの対策を講じることが重要です。
参考までに、経営赤字の種類は多岐にわたり、どの利益がマイナスかによって「経営赤字」や「営業赤字」などと呼び方が変わるため、後述する経営赤字の種類もチェックしてください。
経営黒字との違い
経営赤字は収入よりも支出が多い状態ですが、経営黒字は企業の収入が支出を上回り、利益が発生している状態を指します。
黒字経営を持続することで、企業は運転資金を蓄え事業拡大や新たな投資などが比較的容易に行えます。経営黒字は企業の信用や評価を高める要素ともなり、融資を受けやすく新たな成長戦略を展開しやすくなるでしょう。
しかし、経営黒字であっても必ずしも倒産リスクがないわけではありません。たとえば、大幅な市場変動や競争激化、負債の積み上げなどが原因となり、経営状態が悪化し倒産に至るケースもあります。
経営者は黒字を維持するだけでなく、持続的な成長やリスク管理にも取り組みましょう。
日本の企業の約7割が赤字決算
「決算」は企業が1年間の収入と支出を算出し、決算日時点における財務状況を確定する手続きです。経営者はもちろん、株主、投資家、債権者などの利害関係者にとっても重要な情報源であり、企業の健全性や収益性を判断する指標の一つとなります。
一般法人だけでなく、国や一般社団法人地方公共団体でも決算が義務付けられており、その際に申告した利益に対して課税される「法人税」を支払わなければなりません。
ちなみに、国税庁が公表した「令和2年度国税庁統計法人税表」によると、令和2年度の赤字法人は186万4,249社。全国の普通法人281万8,077社のうち、赤字法人率は66.1%であり、赤字決算している企業が黒字の企業よりも多い状況です。
以上のことから、利益が出ていない赤字決算は企業の節税対策に有効な手段となり、すべての赤字決算が倒産や経営破綻につながるわけではないのです。
また、一般的に新しい事業を開始する際には、初期投資や立ち上げ費用がかかり、収益機会自体がまだ存在しないゆえに赤字となるケースもあります。さらに、経済の変動や市場の競争激化などの要因により、一時的に業績が低下し赤字になる場合もあることから「赤字=倒産寸前」という考え方は誤りといえるでしょう。
しかし、経営戦略ミスで企業の業績が本当に悪化しているパターンや、根本的な事業モデルに問題があり、恒常的な赤字が続くこともあります。もちろん、前述したケースとちがい、こちらは一刻も早く財務改善策を講じなければなりません。
経営赤字の種類

経営赤字になるとすぐ倒産してしまうイメージがありますが、慢性的な赤字でも継続的に経営している企業は少なくありません。
そこでここでは、赤字の知識を正しく身に付けるために、以下4つの種類を解説します。
経常損益の赤字
営業損益の赤字
当期純損失の赤字
現金収支の赤字
経常損益の赤字
経常損益の赤字とは、為替や株式など本業以外の収入で収入と費用の差がマイナスとなる状態を指します。具体的には、企業が本業で一定の利益を上げていても、投資や金融商品の価格変動による損失が発生し、結果として経常損益全体が赤字になる場合などが挙げられます。
一見すると倒産には直結しなさそうですが、本業も赤字の場合は非常に危険な状態といえるでしょう。本業が赤字であるということは、企業の営業活動において収入が費用を上回らず、持続的な損失が発生していることを意味します。このような状態では、資金不足や負債の増加など、経営に大きなリスクが生じる可能性が高まるため、不採算部門の切り捨てなどで黒字転換を図る必要があります。
営業損益の赤字
営業損益の赤字は企業の本業による収入と費用の差がマイナスとなる状態を指します。営業損益は営業活動に関連する収入と費用を計上したものであり、人件費・原材料費・販売費など営業活動に必要な費用が含まれます。
営業損益の赤字は、収益増加やコスト削減といった早急な経営改善が求められ、効果的な経営戦略や費用管理の見直しが重要です。
当期純損失の赤字
当期純損失の赤字は、経常損益に特別利益や特別損失を加減した結果がマイナスとなる状態を指します。特別利益や特別損失には、固定資産の売却損や災害による損失などが含まれることが一般的であり、一時的な赤字のケースが多い傾向です。
経済環境の変化や効率的な資源活用などを通じて、黒字への転換を図ることが求められます。短期的な赤字であっても、持続的な経営には財務改善が必要です。
現金収支の赤字
現金収支の赤字は、現金の流出が流入額を上回る状態を指し、大変危険な状態といえます。
たとえば、現金収支の赤字が継続すると従業員の給与支払いや仕入れ、借入金の返済などの債務不履行が生じる可能性があります。これにより企業の信用度低下から、資金調達が難化し運転資金が足りず、最終的に倒産や経営破綻のリスクが高まるでしょう。
また、損益計算書では黒字にも関わらず計上されていない借入金の返済を行っている場合も同様です。収入より支出の割合が高い状態が続くと手元にある現金が不足するため、帳簿上では順調に利益が出ていても、資金不足から倒産してしまう「黒字倒産」を引き起こす可能性があります。
現金収支の赤字を解消するには、現金の増加策と節約策の両方が必要。具体的な対策としては、売上拡大や顧客獲得の強化、費用の見直し、資金調達の計画的な実施などが挙げられます。現金管理の重要性を認識し、的確なキャッシュフロー予測や適切な資金計画を実施しましょう。
経営赤字のメリット

経営赤字は通常、企業にとっては健全な経営状態ではありませんが、メリットも存在します。あくまで一時的な効果に過ぎませんが、しっかり活用してみてください。
税負担が軽減できる
損失が繰り越せる
税負担が軽減できる
経営赤字の最大のメリットは、法人税や所得税の負担が軽減されることです。法人は決算時に算出された利益に対して課税される法人税を支払う義務があります。しかし、赤字決算の場合は利益が出ていないため法人税がかかりません。
しかし、すべての法人税や所得税が軽減されるわけではなく、法人税であれば均等割りの金額や消費税、他市県民税などの最低限は支払う必要があります。
損失が繰り越せる
赤字決算の場合、赤字分を翌期に繰越し、将来の黒字と相殺し税負担を軽減する「繰越欠損金控除」を利用できます。繰越欠損金控は、一定の要件が定められており、資本金1億円以下の中小企業は最大10年間損失を繰り越すことが可能です。該当期の法人税が免除されるだけでなく、翌年以降の法人税も軽減できます。
また、前年度は黒字で法人税を納めていた場合、税金の一部を還付してもらう「欠損金の繰戻しによる還付」を利用できる場合もあります。
ただし「繰越欠損金控除」「欠損金の繰戻しによる還付」には一定の要件が定められているので、制度利用時には自社が適しているか注意しましょう。
経営赤字のデメリット

経営赤字の場合、法人税や所得税の支払いを最小限に抑えられるメリットもある一方、資金不足や財務への影響、さらに業績への悪影響など、多くのデメリットが存在します。
税務調査の対象になりやすい
融資を受けにくくなる
倒産リスクが上がる
企業の赤字に関する理解を深めるためにも、ぜひ参考にしてください。
税務調査の対象になりやすい
経営赤字が続くと、税務署が不正な活動や申告漏れなどを疑い、調査の目が厳しくなりがちです。実際に、国税庁が公表した「令和3事務年度法人税等の調査事績の概要」によると、悪質な不正計算が想定される法人など、調査必要度の高い約4万1,000件の法人企業に実地調査が実施されています。
黒字経営にも関わらず故意に赤字にしていると、追尾課税などのリスクも高まり、最悪の場合脱税で逮捕される可能性もあるので注意しましょう。
融資を受けにくくなる
赤字経営が続くと、企業の負債が増加し、債務超過の状態に陥る可能性があります。債務超過は、企業の経済的な健全性に悪影響を与え、金融機関からの信頼を失うことにもつながります。
これにより、金融機関からの融資が難しくなったり、取引先からの信頼を失ったりするでしょう。赤字が2期以上続くと、金融機関は融資中断や一括返済を求める可能性があるため注意が必要です。
倒産リスクが上がる
赤字経営では、企業が収益を上げられず、費用をカバーするだけの資金が不足している状態です。資金不足は事業の運営や成長に制約をもたらし、必要な投資や経費の賄いが困難になり、資金繰りの悪化により債務超過に陥るリスクも高まります。
先ほど触れた繰越欠損金控除の制度も、赤字が長期間続く場合にはメリットとはいえなくなります。また、赤字経営が続くと従業員のモチベーションにも悪影響を与える可能性も少なくありません。
安定した業績や給与の支払いが困難になるため、従業員の不安や不満が高まり生産性も低下しかねないでしょう。
経営赤字を黒字化する財務改善方法

赤字経営はメリットよりもデメリットの方が大きく、経営戦略の見直しや財務管理の改善などの取り組みが遅れるほど倒産リスクが高まります。そのため、以下の方法で赤字の要因や問題点を明確に把握し、原因を分析をしましょう。
コストの見直し
キャッシュフローの把握
コストの見直し
経営赤字から脱却する上で、コストの見直しは不可欠といえます。外注費、人件費、広告費、原材料費、販売費など不要なコストを見直し、適正なレベルに抑えることで、経費削減と効率化が可能です。その際、管理コストがかかる過剰在庫を適切に管理し、不必要な費用やスペースを削減しましょう。
また事業戦略の再構築を行い、現状に適した経営計画を策定することも重要です。コスト削減や効率化、新たな収益源の開拓、経営計画の見直しなど、さまざまな手法を駆使して経営の改善を図り、赤字から黒字へ転換できるようにしましょう。
キャッシュフローの把握
経営赤字からの転換においてコスト見直しと同様に、キャッシュフローの把握が重要です。キャッシュフローとは、企業の現金の収入と支出の流れを指します。現金の流れを把握・管理し、企業の資金状態を正確に把握する必要があります。
企業経営においてトラブルはつきものです。資金状態を把握し適切に管理することで、異変があった場合にすぐに対応できるでしょう。
経営分析ツールが示す成長戦略

赤字経営を脱却するには、効果的なコスト管理や収益改善策が必要です。具体的な対策としては、無駄なコストの削減、効率的な業務プロセスの確立、新たな収益源の開拓などが挙げられます。
ただし、すべてマニュアル作業では非効率なため、経営分析ツールである程度オートメーション化するのがおすすめです。
リアルタイムなデータを抽出し、コスト構造や無駄な出費をシステマチックに把握することで、誰でも簡単にコスト項目の分析が可能となり、削減方針を立てられます。
同時に、競合他社や顧客の動向分析も行えるので、自社のリソースなども考慮しつつ、より効果的な成長戦略を策定し、競争力を高められるでしょう。
経営赤字克服には「SubFi for Business」がおすすめ
経営赤字を克服するには、適切な経営戦略とリスク管理の意識を持ちながら、健全な経営状態を維持する必要があります。
また、たとえ赤字であっても企業の持続的な成長や競争力向上につながる可能性もゼロではありません。すなわち、赤字の内容に即した適切な対応が重要であり、経営分析ツールを活用することで、効率的なデータ抽出とリサーチが可能となるのです。
そして「SubFi for Business」は、企業の財務状況やコスト構造を簡単に把握し、誰でも分析に活用できます。効率的な業務プロセスの確立や、購買戦略の立案にも役立つため、ぜひ「SubFi for Business」を検討してみてください。