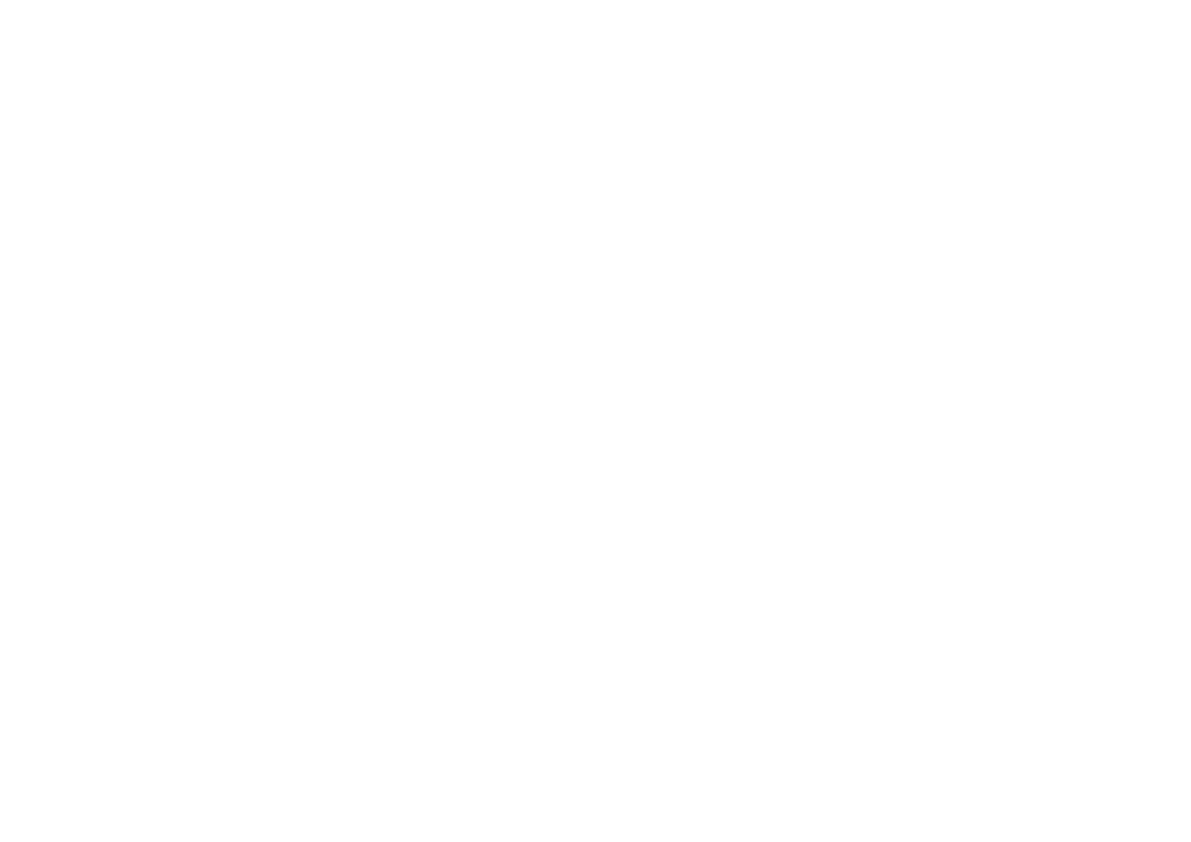企業を経営していれば、当然悩みは次から次へと湧いてくるものです。
そして、そういった「経営課題」は、企業としてありたい姿と現状のギャップが大きいほど深刻化しやすく、まずは問題が何かを特定し、次にどうやって解決していくのかを考えなければなりません。
しかし、いざ課題解決に乗り出そうと思っても、具体的な方法が分からず、そもそも自社の本当の課題が見つけられない企業担当者も多いでしょう。
そこで本記事では、経営課題の概要や実際に企業が抱えがちな問題点、解決策なども解説します。顧客のニーズに応え続け、事業を安定化させるためにも、ぜひ参考にしてください。
企業が抱えがちな経営課題5選

ここではまず、一般社団法人日本能率協会の調査結果をもとに、企業が抱えがちな経営課題の上位5つを確認していきましょう。

参照:一般社団法人日本能率協会「日本企業の経営課題2022」
収益性向上
人材の確保と育成
売上・シェア拡大
ブランド力の向上
新商品・新事業の開発
あらかじめ把握しておくことで、効率的かつスピーディーに対応できるので、しっかり押さえておいてください。
収益性向上
収益性の向上は、企業の根本的な目的の一つであり、資本主義社会における企業の在り方とも言えるでしょう。多くの経営者が収益性の向上を課題として挙げており、最も関心を寄せています。
収益性が低いことは、企業における大きな課題です。収益性が低いことで、中長期的に売上は大きく差が開き、事業の新興スピードなどにも影響を与え、競合他社にも遅れをとってしまいかねません。
そのため、収益性を向上させるには、売上アップはもちろん、営業外費用や売上原価などのコスト削減も必要不可欠です。
人材の確保と育成
「採用がうまくいかない」「すぐに退職してしまう」など、人的リソースに関する悩みを抱えている企業も少なくありません。
参考までに、一般社団法人日本能率協会が公表したデータでは、3年後の経営課題として「人材強化」が上位にランクインしています。採用や育成、多様化への対応を行い、従業員1人ひとりの働きがいや満足度を向上することを課題としているようです。
また、2019年の働き方改革によって、時間外労働の上限や副業解禁など、さまざまな変化に対応する必要も出てきました。すなわち、昨今の企業は、自社に適した人材の確保と従業員のニーズに合った環境構築の両方が求められているのです。
加えて、人的リソースが不足していると、顧客が求めるニーズに対応できず、サービス全体のクオリティ低下を招くリスクがあります。業績に直結する問題となるため、できる限り早い段階で解決するようにしましょう。
売上・シェア拡大
売上やシェアが拡大することで、業界における影響力が大きくなるだけでなく、経営の安定化にもつながるでしょう。さらに、現在参入している市場でシェアを維持できれば、新しい市場にも事業展開しやすくなります。
売上やシェア拡大のためには、客単価の向上や新規顧客の増加などを意識しなくてはいけません。営業力強化のためにも、効率化ツールなどを活用してみるのもおすすめです。
ブランド力の向上
企業として生き残っていくには、競合他社と差別化を図り、自社を選んでもらえるように取り組まなくてはいけません。
ブランド力を向上することで、競合他社より高い価格でも自社を選んでもらいやすくなり、宣伝コストなども削減できるでしょう。
しかし、企業のブランドは一朝一夕で高まるものではありません。製品やサービスの品質はもちろん、さまざまな角度からマーケティング戦略を実践し、継続的に検証を繰り返すことが大切です。
新商品・新事業の開発
近年、AIをはじめとするさまざまな領域の技術が進歩しており、新商品開発などの取組を積極的に行う企業ほど増益傾向にあります。
しかし、新事業展開には「技術・ノウハウを持つ人材の不足」「「コスト負担」などさまざまな課題があり、今一歩踏み切れていない企業も少なくありません。
競合他社に後れを取らず、新しい製品やサービス、新事業の開発などを行い、提供できるかどうかがポイントです。ただし、単に新商品やサービスを打ち出すだけでは失敗する可能性が高い点にも注意しましょう。
経営課題の見つけ方

ここからは、経営課題の見つけ方を5通り解説します。
経営資金の可視化
社員成績の分析
組織状況の俯瞰
業務フローの整理
戦略マップを活用する
経営資金の可視化
お金の流れは、企業の状態を可視化するのに欠かせない項目です。現在は黒字企業でも、倒産に陥る可能性はゼロではないため、常に経営資金を可視化し、自社のお金の流れをきちんと把握しましょう。
こまめに実施すれば、決算期などに再集計する必要がなくなるため、業務を効率化できるメリットもあります。
社員成績の分析
社員の成績を可視化して分析することで、1人ひとりを正当に評価できます。正当な評価は、社員のモチベーション向上にも役立ち、離職率の低下や生産性の向上にもつながるでしょう。
たとえば、下記の指標を表やグラフなどを用いて分かりやすく表示し、問題点を可視化するのがおすすめです。
社員一人ひとりの目標達成度
業務遂行の質
コミュニケーション能力
ただし、グラフ作成のためにすべての社員へヒアリングを行うのは非効率的なので、アンケートなども用いて仕組化してみてください。
組織状況の俯瞰
組織の構造や状況を把握することで「人員の無駄」「能力の偏り」などの経営課題が見つけやすくなります。実は、中小企業は組織図を作成していないケースが多いため、早い段階で作成した方が良いでしょう。
現在の組織状況を把握できていないと、課題の洗い出しや解決に時間がかかってしまうため、こまめに組織の状況を俯瞰的にチェックすることが重要です。
業務フローの整理
既存事業を継続している企業の多くは、業務フローがルーティン化している傾向にあります。業務の効率化が図れるのであれば問題ありませんが、無思考になることで見えない課題が生まれる可能性があるのです。
そこで、業務における必要時間や人材の稼働時間などを毎日算出し、常にパフォーマンスが分かるようにしましょう。
1日あたりの工数のばらつきや社員ごとの生産性などを簡単に把握できるため、課題の洗い出しや業務効率、人材育成の材料としても役に立ちます。
戦略マップを活用する
経営課題を可視化・分析した後は、戦略マップを活用して施策を図にまとめてみてください。戦略マップとは、企業が掲げる目標を達成するために落とし込まれた各施策関連情報を図式化したものを指します。
戦略マップを作れば、経営課題だけでなく、経営戦略の全体像を把握することも可能です。社員全員が戦略の意義や方向性を認識できるため、より組織の意識をまとめられるでしょう。
経営課題を解決する方法

ここからは、経営課題を解決する方法を解説します。
業務プロセスを改善
労働環境の見直し
サービスの量と質の向上
外部コンサルタントの活用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
業務プロセスを改善
業務プロセスを見直すことで、業務の効率化やサービスの質の改善効果が期待できます。
具体的には、モバイルワーク導入やインフラリソースの見直しなどがおすすめです。インフラリソースを見直すことで、経営課題の一つである「事業基盤の強化・再編、事業ポートフォリオの再構築」にも役立つでしょう。
また、社員のライフワークバランス向上にも貢献するため、後述する「労働環境の見直し」にもつながるメリットがあります。
労働環境の見直し
労働環境を見直し、社員が働きやすいよう改善するのもおすすめの解決策です。たとえば、労働時間や個人における業務負担、職場の環境整備などがあげられるでしょう。
働きやすい職場に整えることで、離職率低下を促し、社員のモチベーション向上にも役立ちます。同時に、人事評価制度を構築・見直すことで、目標達成に必要な人材育成にも効果を発揮します。
基本的には、先ほど触れた業務プロセス改善とセットで行った方が効率的です。
サービスの量と質の向上
サービスの量と質を向上させるのも、効果的な解決策といえます。
施策の対象となるポイントとして、サービスの質なら1拠点や1人あたりの売上量、量なら社員数や店舗数があげられるでしょう。量と質の両面を解決することで、売上やシェア拡大に効果を発揮します。
具体的には、優秀な社員の成功事例や最適な方法などを他の従業員にも共有することで、1人あたりの売上向上や社員育成に役立ちます。また、営業スタッフを増員すれば、シェアの拡大にも効果を発揮するでしょう。
外部コンサルタントの活用
経営課題を解決するには、幅広い知識やノウハウなどが必要です。しかし、意外にも知識不足などで経営に不安を感じている経営者は少なくないので、もし不安な場合はコンサルタントなどの専門家に相談してみると良いでしょう。
自社だけでは見落としてしまいがちな問題点をコンサルタントが洗い出し、解決策を導き出すことで、経営課題の早期解決につながります。
ただし、コンサル料を支払う必要があるため、あまり予算に余裕がない場合は、スポットコンサルやスキルマーケットなども活用してコストを抑えてみてください。
経営課題を解決するにはDX化がカギ

ここ数年、経営課題の解決策としてDX化に取り組む企業が増加しています。一般社団法人日本能率協会によると、2022年時点で約半数以上の企業がDXに取り組み、大企業では約8割超に達しているとのことです。
ここからは、DXについて詳しく解説するので、さっそく経営課題の解決に取り入れましょう。
DXとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して新しい製品やサービス、提供価値を創出し、企業の成長を促す取り組みです。ここで言うデジタルとは、AIやloT、ICTなどがあげられます。
経済産業省が発表した「DXレポート」では、現状のままDX推進しなければ、2025年移行、最大で年間約12兆円もの経済損失が発生すると予測されています。
しかし、そんな予測を目の当たりにしても、いまだ日本は世界的にDX化が遅れていることから、もはや日本企業にとってのDX化は急務と言っても良いでしょう。
企業が市場で勝ち抜き、業務効率・競争力を向上させるためにも、DXの推進は必要不可欠なのです。
DXによって得られる解決
DXは何百万もの蓄積されたデータを活用し、経営戦略を立てていくため、定量的データを揃えやすい経営課題の解決に役立つでしょう。具体的には、業務プロセスの改善や生産性向上、マーケティングプロセスの効率化などが代表的です。
また、多くの企業がDX化に取り組む上で、下記の内容も重視しています。
既存商品・サービス・事業の付加価値向上
抜本的な事業構造の変革
新商品・新サービス・新事業の開発
デジタル技術の活用による新規顧客の開拓
たとえば、営業業務ではDXツールを用いて展示会参加企業や成約企業などを可視化すれば、企業の違いを把握することが可能です。
そして、把握したデータをもとに、成約企業のパターンなどを推測し、売上向上に役立てられるでしょう。
「SubFi for Business」で経営課題を効率よく解決しよう

本記事では、経営課題について解説しました。
経営課題を解決するには、在りたい姿と現状のギャップを見つけ出し、課題を解決するために問題を把握して、改善を行う必要があります。その際、自社で浮き彫りになっている課題だけでなく、見えていない課題を発見・解決して、自社の経営をより良くしましょう。
また、経営課題の解決には、ノウハウやITソリューション、DXツールなどの活用が必要不可欠です。SubFi for Businessでは、経営企画の仕事を増やさずに理想とする経営環境を知ることができます。
経営課題を見つけるためのデータ集めや、整形作業を必要とせず、把握・改善を行うことが可能です。また、DX方針の策定なども行っているため、自社のDX化に不安がある場合でも安心してご相談ください。